
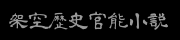
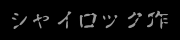

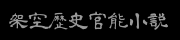
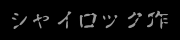
| 第十二話 “天狗の鼻” 男たちは一度の射精だけでは満足することなく、繰返し犯し続けた。 さすがに気丈夫なありさも憔悴を隠し切れず、羞恥も気力も次第に薄れていった。 四人の男たちの精液と汗にまみれた太股がヌラヌラと光り、青臭い臭気を放っていた。 幾度目かの行為が終わった頃、ありさは気を失っていた。 しかし四人の男たちによる凌辱は、これから繰り広げられる更なる恥辱への序幕でしかなかった。 「ふう~、すげぇ締まりのいい娘だぜ。何度やってもすぐにムクムクとおっ立ってきやがるじゃねえか。ぐふふ……」 「お頭の精力はまるで馬並みだぜ」 「それは褒めてるのか?だけどよ、それは好みの女に出くわした時だけだぜ」 「おい、娘、喜びな。お頭がお前のこと好みらしいぜ」 「……」 「あれ?気を失ってやがる。まだおねんねしてもらっちゃ困るんだよな~」 「ところで、平吉。一か月ほど前に白装束の行者から奪った荷物の中に天狗面があったな。あれを持ってこい」 「はて?天狗面を娘に被らせて一体何をするつもりですかい?」 「ばかやろう、娘に面をつけてどうするんだ!」 「はぁ……?あ、そう言うことか……なるほど、えへへへ……」 平吉は頭を掻きながら嫌らしい笑みを浮かべた。 「天狗の鼻で貫いて娘を踊らせるとは一興でござるな」 「最高の酒の肴になるぜ。おい、弥平、酒を持ってこい」 「へい~」 酒が用意され、男たちは気絶から目覚めたばかりのありさを酒盛りの席に駆り立てた。 徳太郎は湯呑にどぶろくを注ぎぐいっと喉に流し込むと自ら天狗面を被った。 「おい、娘、もっと気をいかせてやるぞ」 ありさは徳太郎が被っている天狗面を見て驚いた。 その顔は炎のように赤く、鼻が異様なほどに太い。 しかも先端が男の亀頭を彷彿させるかのように大きく膨らんでいる。 徳太郎は面をつけたまま仰向けになった。 天狗面は天井を見上げてる。 「おい、娘、顔の上に跨るんだ」 汚らわしい一物で処女を奪っておきながら、なおも辱めようと言うのか。 ありさは唇を噛みしめながら、ふと天狗面を見つめた。 鼻の長さは五寸程度と男のそれと比べてもいたって平凡だが、太さが尋常ではなかった。 ありさが今夜受け容れてきた男たちのそれと比べても、優に一周りは太いだろうか。 ありさの表情がこわばった。 (もしかしたら大事なところが裂けるのでは……) 「え……?まさか……そんなことできません!」 「できませんじゃねえんだよ!するんだよ!おい、娘を俺の顔の上に連れてこい!」 突然背後から捨蔵がありさの背中を押し、有無を言わせず徳太郎のもとへ連れて行った。 「やめてください!そんなの無理です!」 「無理かどうかはやってみなければ分からぬものじゃ」 「そんな無体な……」 「さあ、足を拡げて跨ぐのじゃ」 天狗面の真上で開脚を強いられるありさ。 徳太郎が奇声をあげる。 「おおっ!絶景かな~、絶景かな~!生娘の陰門を下から見上げるのもいいもんだぜ!天狗の鼻で可愛がってやるから、早く腰を下ろせ!」 「腰を沈めよ!さあ早く!」 ありさは躊躇している。 「早く沈めよ!お頭に叱られる前に大人しく従う方が利口と言うものじゃ」 「無理です…大き過ぎます……」 「むむむ!どうしても拒むなら力づくで捻じ込むまで!」 業を煮やした捨蔵がありさの細い腰を押さえグイグイと沈め始めた。 「もっと右。違う、もうちょっと上だ」 股間下から徳太郎の指示が飛ぶ。 ようやく照準が合ったようだ。 「よし、そのまま下げろ」 腰がゆっくりと沈められていく。 「やめて…入れないで……」 ありさの表情が恐怖に歪む。 徳太郎以外の三人も挿入の瞬間を固唾を呑んで見守っている。 天狗の鼻が陰門に触れた。 「ひぃっ……!!」 ありさの肩先がぶるると震えた。 鼻の先端がゆっくりと埋没していく。 メリメリという音が聞こえてきそうな光景だ。 ありさは身体を震わせ小さな悲鳴をあげている。 あの凛々しかった女武者の姿が、今では見る影もない。 天狗の鼻が七割方沈められると、ありさの額から脂汗が噴き出した。 眉間に皺を寄せ苦悶する表情が、いっそう男たちの加虐心を煽っていく。 「天狗の鼻で下から突き上げるってのも面白いもんだな。やっているうちに俺の息子も仲間に入れてくれって元気になって来やがったぜ。ぐふふ……」 「本当だ、お頭の股間がビンビンになってら~!」 「おい、娘、お前、今夜はまだまだ忙しくなるぞ!がははははは~」 男たちが冗談話をしている最中も、ありさは苦しそうに喘いでいた。 赤い鼻が陰裂に食い込む様は肉棒とは異なる淫靡さに溢れていた。 再びありさが気絶した頃、天狗の鼻がゆっくりと引き抜かれた。 天狗の鼻から解放されたありさはそのまま床に崩れ落ちた。 気絶したありさに水が与えられ、目覚めると同時に待っていたのは凌辱地獄であった。 逃亡を阻止するため再び手足を縛られると、不自由な姿のまま汚れた欲望の餌食となった。 朦朧とした意識の中、一人の男が果てると、次の男が挑みかかる。時には二人係りで、時には四人で……。 いつ終わるとも知れない凌辱劇は昼夜問わず続けられた。 ありさにはわずかな食事と水が与えられただけで、ろくに休息も与えられなかった。 疲労困憊し薄れゆく意識の中で、幼い頃に見た父幸村の顔が浮かんだ。 (ありさ……負けてはならぬ……がんばるんだ……) そして二日が過ぎ白々と夜が明けた頃、小屋の外に中の様子をうかがう人影があった。 前頁/次頁  |