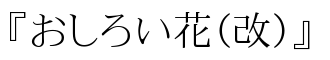
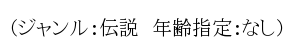
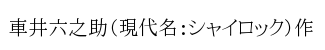
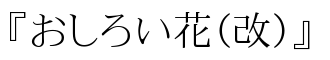 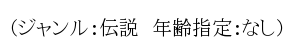 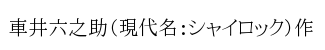 |
 |
| 第三話 今生の別れ 「お万さん、退屈だろう?」 「いえ、そんなことはございませぬ」 「そなたも釣りをやってみるか?」 「いいえ、私は維盛さまのその凛々しいお姿を見させて戴いているだけで、幸せにございます」 「なんと、可愛いことを……」 昼間は他人の目もあって叶わなかったが、夜更け、皆が寝静まってから、ふたりは木陰で逢う瀬を重ねた。 抱き合い、唇を重ね合い、いつしかふたりは男女の契りを交わした。 お万が小森に来てから、三度目の夏を迎えたときのことであった。 その日も、お万はいつものように井戸端で洗い物をしていた。 石童丸のところへ二人の男がやって来た。 石童丸「おお、衛門、それに嘉門ではないか。久しぶりでござる。よくぞ参られた」 お万は咄嗟に、井戸の陰に隠れた。 衛門「維盛様はいかがなされておる」 石童丸「うん、そうだな。今はお万というおなごに惚れておられて、かって屋島の戦で見せられたほどの元気をなくしておられる」 嘉門「それは、よくありませぬ。平家の再興のため、お元気を取り戻して戴かなくてはなりませぬ」 石童丸「解っておる。解ってはおるが……」 お万「えっ!平家……」 お万は驚きを隠せるはずがなかった。 それと言うのも、維盛という名は聞いてはいたが、まさか平家とは露にも思わなかった。 この三年というもの、維盛たちは自分たちの素生を明かそうとしなかった。 もちろん、お万も聞いてはならぬと思い、一切そのことには触れようとしなかった。 まさか今まで世話をして来た殿方が、世間を騒がせている平家の一門の方々とは……。 お万は動揺した。 その時であった。 お万は足元の桶にけつまずき、ガタリと音を立ててしまったのだ。 嘉門「何者だ!」 石童丸「あっ、お万さん……」 お万は唖然として立ち尽くしていた。 石童丸は声も出さず、お万の驚く顔をじっと見つめていたが、表情を和らげて語った。 石童丸「お万さん。今まで隠していてすまなかった。実は、今聞かれたとおりなのだ。維盛様は、平家再興のための大事なお方。それに、この地も、追っ手に気付かれそうなのだ。秋には引きはらって、別の隠れ家に移らなければなるまい。どうか、維盛様のことを思われるならば身を引いてくだされ」 立ち尽くすお万の眼から涙が溢れ落ちた。 お万はその日以来、悲しみにくれ、見る見るうちにやつれていった。 しかし、維盛にだけは心配させるまい、気付かれるまいとして、お万はけんめいに涙を堪え、明るく振る舞った。 お万の悲しみこそ気付かなかった維盛であったが、お万に夢を馳せていた。 今は無理なことだが、いつかきっと、平家再興の暁には、お万を都に呼びよせて、幸せにしてやりたいと心に誓っていた。 小森にも秋がやって来て、とうとう別れの日が訪れた。 お万は維盛を峠で見送ることにした。 維盛「お万、上湯川は良い所だそうじゃ。向こうに着いて落ち着いたら、必ずおまえを呼び寄せる。その時まで、元気におられよ」 これが今生の別れになるとは夢にも思わぬ維盛は、こんな優しい言葉を掛けたのだった。 お万はこの言葉を聞いて、思わず涙ぐんだ。 遠ざかっていく維盛の姿をいつまでも見送った。 どうぞご無事でと……。 とうとう姿が見えなくなったが、お万はいつまでもいつまでもその場に立ち尽くしていた。 維盛が去った後、何日経っても、お万は想い出深い小森の地を離れなかった。 ある夜明けのことだった。 誰かが戸をドンドンと叩くではないか。 「お万さん、お万さん……」 戸を開けてみるとそこには、悲壮な表情の重景が立っていた。 お万「あ、これは重景様、いかがなさいましたか?」 重景「こ、維盛様が……」 お万「えっ!!」 お万の顔は見る見るうちに血の気を失って行った。 言葉を失い、ただただぼう然と立ち尽くすだけであった。 重景の話によると、維盛たちが小森を立ったあと、すぐに味方が追いかけて来て、平家一門の崩壊を告げたとのこと。 これを聞いた維盛は愕然としながらも、冷静さを失わず、「もしかすれば、これは罠かも知れぬ」と考えた。 維盛は、ひとり山頂へ登った。 そして、護摩を焚いた。 その煙が上へ登れば、知らせは嘘。 下へたちこめたら真実……という賭けをしたのであった。 しかし維盛の願いは空しくも、煙は下へ下へと這って行ったという。 平家も最早これまで……。 維盛は、それ以来、行方知れずになってしまったと言う。 お万は、すぐに着物を一番きれいな小花模様に着替え、髪をとかすと、お白粉と紅を持って小屋を出た。 戻る/進む |
