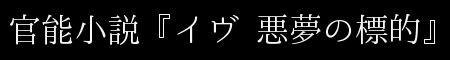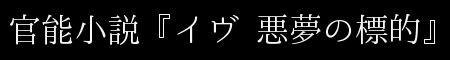第11話 イヴは腹部を押えて苦悶の表情を浮かべている。
「お、お願いです・・・トイレに行かせてください・・・」
上野はにやにや薄笑いを浮かべるばかりで便所の場所を指示しようともしない。
「ひぃ~!もうダメです!も、もう漏れそうです!お願いっ!」
イヴは額に脂汗を浮かべて上野に懇願した。
上野はようやく重い口を開いた。
「便所は廊下をずっと真っ直ぐに行って一番右奥にあるよ。そんな所まで歩けるかな?途中で漏らしてしまうんじゃないのかね?」
「ううっ、うううっ・・・」
「廊下で漏らしたくなければこの便器で用を済ますことだね。ははは、ただし会長や私に排泄の現場をしっかりと見られてしまうがね」
「それは嫌です!」
「じゃあ、廊下へ出るんだね」
上野はイヴを突き放つようにそう告げて、便器を取り除こうとした。
「ま、待って!」
イヴの便意はすでに限界に達していた。
本来ならば男たちの目前で排泄するような醜態を晒すことなど到底考えられない。
しかし今はそんなことを言っている余裕はなかった。
「ああダメです・・・出ます、出ます・・・ああ、お願いですっ・・・ここでさせて・・・ああ、せめて、せめてあっちを向いててください!」
イヴは今にも泣き出しそうな声で哀願した。
「よし、分かった。よそを向いててあげるから直ぐにしなさい」
今にも漏れそうでイヴの身体がぶるぶると震えている。
しばらくすると恥辱の音とともにプラスチック製の便器に黄金水が噴出した。
次の瞬間、上野がシャッターを切り始めた。
(カシャッ!カシャッ!)
「や、やめてください!撮らないで!」
イヴはすがるように訴えかけたが、上野はそれを黙殺しデジカメを構え撮影を続けた。
まもなく排泄が終了した。
「すっきりしたかね?ははは、それじゃ私がお尻を拭いてあげよう」
「け、結構です・・・自分で、自分で拭かせてください」
「そんなに遠慮しなくてもいいじゃないか」
上野はイヴの臀部にガーゼを宛がいきれいに拭きとった。
イヴは恥ずかしさのあまり消え入りたい心境であった。
「お尻を洗いたいんですけど・・・」
イヴはぽつりとつぶやいた。
「でもここにはウォシュレットはないしねえ。あ、そうそう、奥にシャワー室があるからそこでシャワーを使いなさい」
「は、はい・・・」
イヴは腕の拘束を解かれ、跡形のついた手首をさすりながらシャワー室に向かった。
その後姿を眺めていた阿久夢が上野にささやいた。
「ふふふ、部長、私もいっしょに入るよ。君は来なくていいからね」
「あ、はい、分かりました・・・」
「私もすでに68才。あんなに若くて美しい娘といっしょにシャワーを浴びれることなどそうそうないだろうからね。ふふふ・・・悪いが君は次の準備をしておいてくれ」
上野としてもできるだけ会長である阿久夢の機嫌を取っておく方が、今後の自分の立場がより磐石になるということを十分に理解していたが、その彼としても日頃から目をつけていたイヴを会長に独占されることはまるで“鳶に油揚げをさらわれる”ようなものあり、決して快くは思っていなかった。
阿久夢は先にイヴの入っているシャワー室の扉を開ける。
病院のシャワー室だから内側から鍵は掛からない。
「きゃぁ~~~~~!!」
ちょうどシャワーを浴び始めたばかりのイヴは、突然阿久夢が入ってきたので思わず驚きの声をあげた。
「出て行ってください!」
「まあ、そうつれないことを言わなくてもいいじゃないか。ぐふふ・・・」
阿久夢は一糸まとわぬ姿でシャワーを浴びるイヴを舐めまわすように見つめた。
「「か、会長、お願いです!シャワーだけはひとりで浴びさせてください。お願いします!」
「そう邪険にしなくても。すでに身体の隅々まで覗かれた後なんだし。今さら何を言ってるんだね」
「ほ、本当に嫌なんです・・・シャワーの時だけは・・・」
「まあ、そう言わずに、どれ、シャワーを貸してごらん」
阿久夢は有無を言わさずイヴの持っていたシャワーヘッドを強引につかみ取った。
第12話 そして二の腕をつかみ、シャワーヘッドをイヴの肩先胸元に向けた。
シャワーしぶきがイヴの身体を濡らす。
さらにはしぶきの方向に合わせて厳つい指をイヴの身体に這わせた。
「いや・・・」
「そんなに私を避けなくてもいいじゃないか。それにしても早乙女君は本当に良い身体をしているねえ。このすべすべとした肌触りは最高だよ。それに、ふふふ、おっぱいの形も申す分ないしね」
そう言いながらいって小ぶりの乳房をぎゅっとつまんだ。
「か、会長、許してください・・・」
阿久夢はイヴの背後から乳房のみならず、肩、腰、さらには腹部などを撫でた。
それは若い男性の迅速なそれとは違ってゆっくりとした老獪な動作であった。
動きの1つ1つは緩慢なのだが、女の身体の隅々まで知り尽くしているのか、性感のつぼを的確に探り当てた。
「か、会長、いやです・・・あ、そこは・・・やめてくださぃ・・・」
シャワーしぶきで背中を流しながら阿久夢の唇が這い回ると、イヴは強く感じたのかびくりと身体を波打たせた。
「ふふふ・・・早乙女君の背中は性感帯の宝庫だね。探り当てるのが楽しみだよ。どれ、ここはどうだね?」
「ひ~っ・・・そこはぁ・・・」
阿久夢は後方からイヴを抱きしめながら、しずくでぐっしょりとなった黒い茂みに指を這わせた。
「ああっ・・・」
(クチュクチュクチュ・・・)
それは谷間にしずくが浸みていたからか、それとも内部から蜜が湧き出ていたのかは分からなかったが、いとも悩ましげな水音が阿久夢の耳に届いた。
「ほほう、早乙女君のここはまるで楽器のようじゃ。いい音がするのう。ふっふっふ、どうじゃ、こうして擦ると気持ちが良いじゃろ?」
「気持ち良くなんかありません・・・お願いです、もうやめてください・・・」
「これぐらいではまだ気持ちが良くないのか?ではもっと奥の方を擦ってやろう」
「いやぁ・・・」
阿久夢の指はさらに奥地へと食い込んでいった。
(グチュグチュグチュ・・・グチュグチュグチュ・・・)
阿久夢は内壁を擦るだけではなく、抽挿を繰り返したり捏ねたりと、あらゆる指の動作を試みた。
「あああっ・・・か、会長、い、いやですぅ・・・お願い・・・もうやめてぇ・・・」
「ふふふ、かなり感じてきたようじゃな?どれ、実(さね)を少し可愛がってやろうかのう。早乙女君、そこに座りなさい」
浴槽の縁に腰を掛けるよう指示されたイヴは仕方なく腰を降ろした。
「そんな膝を閉じたままだと可愛がってやれないではないか。ささ、思い切り脚を広げなさい」
阿久夢の口調はあくまで穏やかではあったが、決して拒むことのできない威厳があった。
イヴは頬を紅潮させながらゆっくりと脚を45度ほど開いた。
「そんなんじゃだめ。もっと開きなさい」
イヴは観念したかのようにさらに膝を広げる。
45度から90度へ。
「もっと・・・」
「えっ・・・?」
脚は扇のように開き、120度ぐらいに広げられた。
秘裂も同時に広がってしまい、その内部の美肉までもあらわにしていた。
「そのぐらいでいいだろう」
阿久夢は満足そうな笑みを浮かべ、腰を折り曲げイヴの股間へと顔を近づけた。
年輪を重ねたことが証明されるような皺くちゃの指がクリトリスに触れた。
「あっ・・・!」
実を覆う包皮が老獪な指にゆっくりとめくらていく。
まもなく可憐なピンク色の真珠が姿を現した。
第13話 「ふふふ、愛らしい実が生っとるのう」
阿久夢は舌をぺろりと出しピンク色の真珠を舐め始めた。
最初は味覚を楽しむかのようにゆっくりと舐めていたが、まもなく阿久夢の舌は左右に蠢動を始めた。
(レロレロレロレロ・・・レロレロレロレロ・・・)
「あぁぁ・・・そこはぁ~・・・あぁ、いやぁ~~~~~~・・・」
痺れるような快感が五臓六腑を駆け巡り、堪りかねたイヴはすすり泣くような声を上げた。
「あぁぁぁ~~~、か、会長、そこはぁ~・・・ああぁぁぁ、あぁ、困りますぅ~・・・会長お願いです、もうやめてぇ~・・・あああ~~~・・・!」
年季の入ったクリニングスは間断なく続いた。
それは陰核を攻めるだけと言うのに実に多彩な舌技を駆使し、ついにはイヴに艶声を奏でさせてしまった。
イヴとしても感じるまいと懸命に耐えてはいたのだが、年頃の娘に肉体の疼きを止めるすべはなかった。
やがて呼吸は乱れアクメの兆しを呈していた。
「あああ~~~っ!だ、だめですっ!ああっ!イキそう!あっ、あっ、あっ!ああああああああああ~~~~~!!」
「ふふふ、イッてもいいんだよ。ふふふ、さあイキなさい」
「あぁぁぁ~~~~~~~~~~~!!」
イヴは背筋を反り返らせながら、ついにはアクメの声を発してしまった。
阿久夢は満足そうに微笑みながら、間髪いれず息を荒げるイヴに声をかけた。
「早乙女君、良い目をしたのだから今度は君がお返しをする番だよ」
そうつぶやきながら年甲斐もなく激しく怒張させたイチブツを、イヴの口内に押し込んできた。
最初は顔を背けるイヴであったが、まもなく諦めたのか怒張した肉棒を咥えた。
(ジュパジュパジュパ、ジュパジュパジュパ・・・)
「ううう・・・もっと舌を使って・・・。そうそう、もっと喉の方まで・・・」
何かと注文の多い阿久夢ではあったが、まるで魂の抜けた人形のように彼の言葉に従うイヴの姿があった。
瞳からは一筋の涙が頬を伝った。
口内に押し込まれた阿久夢の物体が一段と硬さを増していた。
そしてついに、イヴにとって最も辛い時間がやって来た。
先に阿久夢が浴槽の縁に腰を掛け、向かい合って座るようイヴに指示をした。
座位で下から貫こうと言うわけだ。
「会長、お願いです。それだけはどうか許してください。私には彼氏がいるのです・・・」
「ほう、彼氏がいるのか?君に彼氏がいたって別に構わないがね」
「いいえ、私が・・・私が困るんです・・・」
「そんなに困らなくてもいいじゃないか。どうせその彼氏といつもこんな嫌らしいことをしてるんだろう?ぐふふ・・・」
「・・・・・・」
阿久夢はためらうイヴの腕をひっぱり自分の方へたぐり寄せた。
「どうしても逆らうのなら、後から恐ろしいお仕置きをすることになるけど・・・いいんだね?」
阿久夢は凄んでみせた。
イヴの脳裏にさきほど見たさまざまな医療器具が浮かんだ。
恐怖がイヴを支配した。
「わかりました・・・」
がっくりと肩を落としたイヴは阿久夢に近づいた。
だが目前にそびえ立つイチブツをとても正視できない。
目を背けたまま阿久夢の膝にゆっくりとまたがり腰を下ろしていく。
イヴの可憐な渓谷の真下には、それをまもなく貫こうとしている肉槍が待っている。
それはイヴにとっては凶器以外の何物でもなかった。
肉槍が渓谷に触れた。
「う・・・」
(ズニュ!)
「あああっ・・・」
(ズズズン!)
阿久夢は膝にまたがったイヴの背中に腕を廻しぎゅっと抱きしめた。
そしてイヴの耳元でささやいた。
「ふっふっふ・・・まもなく70才を迎える私がまるで孫のような娘の秘所を貫いておる・・・ぐっふっふ、まるで桃源郷にでも行ったような心地じゃ。ぐふふふふふ」
阿久夢はひとり笑みを浮かべ、ゆらゆらと波間をさまよう小舟のようにイヴを揺すった。
第14話 (グッチョグッチョグッチョグッチョ・・・)
「いやぁ・・・やめてください・・・」
阿久夢の魔手から逃れようと必死にもがくイヴ。
だが身体の中心部に太い肉杭を打ち込まれ、さらには背中もがっちりと阿久夢の腕に固定されていては逃れるすべはない。
感じるまいと思ってはいても、体内に沸き立つ何かを抑えることは困難であった。
欲情とは稀にその女性の意思とはうらはらに一人歩きすることがある。
身体の奥底からじわりじわりと迫り来る激しい疼きがイヴを包み込んだ。
「あぁっ・・・あぁぁぁ~・・・」
阿久夢の動きが激しさを増した。
イヴの腰はそれに合わせて上下動した。
「あぁぁぁっ・・・いやっ・・・ふはぁ~・・・ああぁ~・・・」
さすがに年齢的なものもあって発射までに時間を要したが、それでも大量の白い液体をイヴの身体深くに注ぎ込んだ。
膣内射精されることを直前に察知したイヴは阿久夢から離れようと懸命にもがいたが、阿久夢はそれを許さなかった。
「はぁはぁはぁ・・・早乙女君、すごく気持ち良かったよ。ん?もしかして赤ん坊を心配しているのか?ははは、もしできても私がちゃんと面倒を見てあげるから心配しなくていいよ」
イヴは返す言葉が見つからなかった。
一時的ではあるがようやく阿久夢から解放されたイヴは、その汚された身体を丹念にシャワーで洗い流した。
特に繊細な部分は丁寧に洗った。
亀裂からはねっとりとした液体が溢れ出てくる。
イヴは口惜しさに唇を噛み締めた。
阿久夢の精液は一滴たりとも体内に残したくない。
イヴは執拗に洗浄を繰り返した。
その頃、シャワー室の扉に耳を当て、内部の様子を伺っている男がいた。
それは上野であった。
上野はふたりの会話の一部始終を聞き、地団駄を踏んで口惜しがっていた。
(くそ・・・いまいましいじじいめ!早乙女イヴを一人占めしやがって・・・)
嫉妬の炎に燃え狂いながらも、シャワー室内での痴態劇を想像しひとり興奮を膨らませていた。
まもなく全裸のイヴがシャワー室から出てきた。
バスタオルで身体を拭った後、そのバスタオルを身体に巻きつけようとした時、上野から絶望的な言葉が浴びせられた。
「バスタオルは巻かなくていいよ。今から研修の2時限目だからね」
「えっ!?まだあるんですか・・・?お願いです・・・もう許してください」
「勝手なことを言うんじゃないよ。さあ、汗を拭いたらそこに横になりなさい」
上野は高圧的な態度でイヴに対して診察用ベッドへ横になるよう指示した。
「仰向けに寝なさい」
天井を仰ぐ姿勢で寝転んだイヴをすぐに上野は慣れた手つきで革ベルトで拘束を開始した。
イヴの膝頭は顔に届くほどに大きく折り曲げられ、両手両足はそのまま固定されてしまった。
「何をするのですか!?」
「ふふふ・・・」
全裸で仰向けに寝かされそのうえ屈曲位の格好になると、股間が完全に露出してしまうため、女性にとっては四つん這い以上に屈辱的姿勢と言えた。
阿久夢は椅子に腰を掛けて、イヴが縛られる様子を楽しそうに眺めていた。
「実に良い眺めだね。早乙女君の彼氏がもしこの光景を見たとしたらどう言うだろうね。ははははは」
横合いから上野が口を挟む。
「今ここにもし彼氏がいたらたぶん気絶するんじゃないですかね。いや、案外自分の彼女のいやらしい姿を見て激しく興奮し発射させまくりかも知れませんね。がっはっはっはっはっは~!」
「ほほう、それは愉快だね。ははははは~」
「・・・」
イヴは彼らの卑猥で下劣な会話から顔を背けた。
まもなく上野がイヴの目前にくねくねと蠢くバイブレーターのようなものを取り出した。
「さあて、早乙女君、次はこれを使おうと思うんだがね。ふふふふふ」
だがよく見ると、それはイヴが知っているバイブレーターやローターとは少し違っていた。
第15話 「早乙女君、君は今までバイブレーターを使った経験があるのだろう?ははは、当然あるよね?」
「・・・・・・」
「ははは、まあいい。実はね、これは私が作った試作品なんだよ。今までのバイブとはかなり違うんだ。今までのバイブは電気機器や精密機器に詳しいいわゆるエンジニアたちが作っていた。つまり医学知識の無い人たちが作っていた訳だ。でも私は医者だ。産婦人科医ではないが、女性の身体は機会ある毎に研究をしてきたから、性感帯も熟知している。本来、ヴァギナというものはクリトリスと比べたら感じにくいとされている。しかし、クリトリスよりも鈍いとされているヴァギナにも激しく感じるポイントが2ヵ所ある。その1つがおなじみのGスポットで、もう1つはヴァギナの最奥で子宮口入口にあるポルチオ性感帯、略してPスポットと呼ばれている箇所だ。ところが今までのバイブではGスポットは攻めることのできるバイブは開発されていたがPスポット専用のバイブは位置的に困難とされていた」
「・・・」
「だけど私が作ったこのバイブを使えば、攻めにくいPスポットを簡単に刺激し、女性は何度も押し寄せるエクスタシーに最高の快感を覚えることになるだろう。やがて連続して絶頂を体験し、時にはあまり良すぎて失神するかも知れないがね。ははははは」
「・・・」
「で、今からこれを君に試してみてあげようと思ってね。眠っている君の性感を呼び覚ましてあげるからねよ。楽しみだろう?」
「いいえ、結構です。お断りします。とにかく早く拘束を解いてください」
「まあ、そんなに遠慮しなくてもいいじゃないか。記念すべき第1号なんだし。ははははは~」
イヴがいくら拒絶しようとも、上野は意に介する様子など微塵もなかった。
「でも突然入れると痛いかも知れないので少し濡らしてあげようかな?」
「や、やめてください・・・」
「いやいや、先程シャワー室で会長にしっかりと可愛がっていただいたからその必要は無いかな?」
「そ、可愛がってなんかもらってません・・・」
「ふむ?本当かな?まあいい、その辺はあまり詮索しないでおこう。ははは」
上野はそうつぶやきながら、恥辱の姿で固定されたイヴのそばに近づいた。
煌々と輝く天井のライトは縦に走った女の証明を鮮やかに映し出していた。
拘束されていなければ男の視線から逃れるため、脚を閉じ合わせて隠すこともできるのだが、開脚海老縛りに固定されては隠すすべが全くなかった。
そんな無防備な姿からはサーモンピンク色した内部の襞さえも丸見えになっていた。
上野はゆっくりと溝に沿って指を這わせた。
「あぁ・・・そこはぁ・・・」
次第に指は亀裂の中に埋没していく。
もうすでに第1関節まで隠れてしまった。
「あっ・・・」
「早乙女君のここは色素も薄くてとてもきれいだね。吸いつきたくなるよ」
「あぁぁぁ~・・・」
「吸ってもいいかな?」
「いやぁ・・・」
「ふふふ、女の『いや』はオーケーの合図だとよく言うよね?」
「いやっ・・・本当に嫌なんです・・・」
「何を今さら」
上野は溝に舌を沈めた。
(ムチュ・・・)
「ああっ!」
(ペチョペチョペチョ・・・ペチョペチョペチョ・・・)
「あぁぁ、やめてください!」
腹を空かした獣が餌を漁るように、上野は突然激しくむしゃぶりついた。
「ああっ、そんなぁ!いやっ!う、上野部長・・・や、やめて・・・ください・・・!」
「いつも彼氏にこんなことしてもらってるんだろう?いつもはどんな声を出しているんだね?私の前でも実演してくれよ」
上野はクンニを小休止し、つまらないことをイヴにささやく。
当然イヴから返事はなく、上野は再び行為を続行する。
先程よりも乱暴に、割れ目に舌を捻りこませ孔をほじるように律動させる。
(ジュパジュパジュパ、ヌチョヌチョヌチョ・・・)
「ふはぁ~・・・あぁ、いやぁ~・・・お願いです・・・ぶちょお~、やめてぇ・・・」
「ふふふ、かなり濡れて来たね。ぼちぼちいいかな?じゃあ、入れるとしようか」
上野はバイブを亀裂に宛がいゆっくりと挿入を始めた。
「あっ・・・」
(ズニュ~)
上野の表情は真剣そのものである。
横合いから見つめる阿久夢もその光景をじっと見つめている。
バイブがゆっくりと沈められていく。
「あっ、あああ~っ・・・あっ、あっ・・・あああぁぁ~~~・・・」
10/
16