
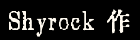


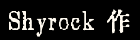

| 第一話 「女中奉公」 時は大正八年、まだ春遠い二月中旬のことであった。 瀬戸内海のとある小さな島から大阪の商家へ奉公に出された一人の娘がいた。 名前を『ありさ』といい、歳は十六で目鼻立ちの整ったたいそう器量のよい娘であった。 ありさの家は畑を耕し細々と暮らしていたが、運悪くここニ年、雨がまったく降らず日照りが続き、作物は実りの秋を待たずにほとんど枯れてしまった。 家は両親と子供五人の七人暮らしであったが、たちまち食べる物がなくなり困り果ててしまった。 このままでは一家心中しなければならない。 困り果てた両親は口べらしのため、一人を奉公に出すことにした。 ありさは五人きょうだいの三番目で、上の二人は男で畑を手伝い、下の二人はまだ幼い。 そんな事情もあってありさが奉公に出されることになってしまった。 「すまねえな、ありさ、達者でな」 「くれぐれも身体にゃぁきゅぅつけてね」 「うん」 「クスン……おねえちゃん……」 「せぇじゃ、行ってくるね」 村のはずれまで見送ってくれた家族に別れを告げ、ありさは涙を堪えながら去っていった。 ◇◇◇ ありさが奉公に訪れたのは大阪船場に店を構える『霧島屋』という呉服問屋であった。 ありさが大阪に着いて最初に驚いたのは、街の活気と行き来する人の多さであった。 いや、それ以上に驚かされたのは、ありさの家とは比べものにならないほどの、屋敷の広さと立派な構えであった。 店主の霧島九左衛門は今年五十八歳で、目尻が垂れ下がり、胡坐をかいたような大きな鼻を持ち、まるで七福神の布袋様のように腹が出ており、見るからに好色そうで脂ぎった印象の男であった。 その印象にたがわず、つね日ごろから女癖が悪く、人妻、後家、店の女中、貧乏長屋の娘と様々な女性に手をつけていた。 金銭に関しては利得に抜け目がなく、呉服問屋を営むかたわら、裏ではちゃっかりと高利貸しをやっていた。 ただし高利貸しに関しては金儲けだけでなく別の目的があった。 経済的に行き詰まった男性に高利子で金を貸し、返済日までに返さなかった場合、利息の代わりにその妻や娘を担保に取り手籠めにするなどかなりあくどい事にも手を染めていた。 当時、旦那衆の中には芸者遊びや遊郭に呆ける者も数多くいたが、九左衛門の場合、それら玄人遊びには全く興味を示さなかった。 ありさが霧島屋にやって来た日、九左衛門の目がキラリと輝いた。 優艶とは程遠いが、いかにも田舎娘といった素朴さの中に、かつて見たことのない清廉な色香をありさの中に感じたのだった。 九左衛門はその垢抜けないあどけなさを残す純朴美少女に見惚れていた。 「名前はなんちゅうねん」 「ありさです」 「いくつや?」 「十六です」 「大阪は初めてか?」 「はい、初めてです」 「両親からどんな仕事か聞いてるか」 「いいえ、聞いてません」 「そうか、うちは着物の卸問屋や。くわしいことは後で上女中から説明させるわ」 「はい、分かりました」 「難しいことは言わへんけど、大事なこと一つだけ教えといたるわ」 「はい」 「絶対わしに逆ろうたらあかん」 「はい……」 「わしの言うことは絶対に従うんやで、ええな」 「はい……」 「もし逆ろうたら……」 「はい……」 「一膳、飯抜きや」 「……」 「もし何回か逆ろうたら店をやめてもらう。ええな?」 「は、はい……分かりました……」 「おまえ自身もかなりの決心をして来たんやろし、たやすく家に帰るわけには行かへんやろ?」 「はい……そのとおりです」 「そやったら、せいぜい気張ってわしに尽くすこっちゃ」 「はい」 「ええか?」 「はい、分かりました」 「よっしゃ、分かったらもうええ。ほんなら向こうに行って、仕事を教えてもらい」 「はい、それでは失礼します」 ありさは両手を畳につけて深々と頭を下げると部屋を後にした。 ありさが部屋から出ていくまでの間、九左衛門はありさの後ろ姿をいやらしい目つきでじっと見つめていた。 もちろんありさはそれに露ほども気づいていなかった。 「ありさか……。まさかあんな器量のええ娘が来るとはな。ほんまにびっくりしたで。歳は十六か。想像するだけでよだれが出て来たわ。どんな肌しとるか、脱がすのが楽しみやで……」 九左衛門の股間は想像しただけで大きく盛り上がり、垂れた目尻を一段と下げていた。 「ぐふふふふふ……」 部屋で一人、九左衛門は淫らな妄想を膨らませながら、だらしなく口元を緩めていた。 しっかりと使い込んでよく鞣した麻縄を握りしめて。 次頁  image 表紙 自作小説トップ トップページ |