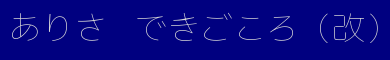 |

| 第6話 「じゃあ言われたとおりにするんだな」 「わ、分かったわ……」 平手打ちを食ったありさはすっかり怯えている。 その後も車野山の紅筆による卑猥な行為が続いたが、全く湿ってくる気配がない。 被虐願望のある女性なら打たれて濡れるかも知れないが、ふつうは打たれたら気持ちが昂ぶるどころか反対に萎えてしまうだろう。 車野山は紅筆による責めを断念し、すぐに同様に卓上にあるありさの携帯電話を握りしめた。 「この携帯、マナーモードにしてもらおうか」 「え?いったい何をするんですか?今マナーモードの設定になっていますけど……」 「それなら手間が省ける」 「……?」 車野山は何を企んでいるのだろうか。 ありさは訝しく思ったが、余計な質問はプラスにはならないと考え、それ以上の質問は控えることにした。 車野山は赤外線通信を使ってありさの電話番号を自身の携帯電話に受信し終えると、にっこりと笑った。 ありさは不安の色を滲ませている。 「心配しなくてもいい。僕はストーカーじゃないから用が済んだらちゃんと消してあげるから」 「いったい何をする気なの」 「ふふふ、すぐに分かるよ」 「……」 車野山はありさに携帯電話を返しポツリとつぶやいた。 「それをしっかりとクリトリスに密着させて」 「え~っ!?そんなこと!」 「できないって言うの?」 「や、やります……」 ありさは受け取った携帯電話を自身の股間にあてがった。 「もっとしっかりと押しつけて」 「はい……」 「よし、それでいい、絶対に放しちゃいけないよ」 車野山は電話をかけた。 もちろんかけた先はありさの携帯電話だ。 まもなくありさの股間に密着させていた携帯電話が受信を告げる振動を開始した。 「いやぁ~~~~~~~~~!」 性具のバイブレーターやローターとは比べものにならないくらい微弱な振動ではあるが、今のありさにとっては十分過ぎるほどの振動と言えた。 ありさが大声を出したため、車野山は思わずありさの口をふさいだ。 「おい、静かにしろ!」 「うぐうぐうぐ!!きゃぁあああ…!!うぐぐぐぐ!!」 「あまり大声を出すとタオルで口を縛るぞ!」 「やめて!声を出さないからそれはやめて!」 「じゃあ、いくらクリトリスを責められても声を出すなよ、いいな!」 「くっ……うううっ……くぅ~~~……」 「絶対に手を緩めるなよ、いいな、強く押さえてるんだぞ」 「はい……あぁぁぁぁ~~~……」 一定の呼び出し回数が終了すると留守電に切り替わってしまうことから、車野山は留守電機能を解除するようありさに命じた。 つまり車野山の気が済むまで果てしない責めが続くことになるわけだ。 「もうだめ!刺激が強すぎるよ~、もう許してください!」 「ほほう、そんなに効くのか?じゃあ、もう少し継続だ。自分でクリトリスの皮をめくってそこにピタリと当ててくれるかな」 「うそ!そんなことしたら私狂ってしまいます!」 「いいや、ダメだ。言うとおりにしてもらおう。大学を辞めたく無ければな」 「ひ、ひどい……」 ありさは車野山の指図に従い、震える携帯電話を剥き出しにしたクリトリスにピタリと押し当てた。 「きゃぁぁぁぁぁ~~~ダメダメ~~~……いやぁぁぁぁぁ~~~!もう許してぇ~~~!」 「ふふふ、その調子だ。お汁が太ももまで垂れだしたら許してやるよ。それまではダメ!」 「そんなぁ~~~そんなの無理~~~ひぃひぃ~…ひやぁぁぁぁぁ~~~!!」 ありさはそうつぶやいてはみたが、携帯に隠れて見えない部分から半透明の液体がわずかに滲み出していた。 「ふふふ……まだまだ。もっと強く押し当てて!」 「いやぁぁぁぁぁ~~~!もう許して~~~、変になっちゃうよ~~~!」 振動は充電が切れるか、本人の意思で続行を中止しない限り、果てしなく続くのだ。 「やんやんやん~!あはぁ~あはぁ~あぁぁぁぁぁ~~~~~~~~~~~~~~!!」 ついに一筋のしずくが太ももを伝った。 「もう頃合いかな」 車野山はそうつぶやくと、ありさの携帯を奪い取り、すぐさま亀裂の中心部に中指を挿し込んだ。 「きゃっ!!やめて!!」 「ほう、ここはもう梅雨みたいじゃないか。ぼとぼと~!」 「そんな恥ずかしいことを言わないでぇ……」 「ここはどうかな?」 車野山は中指と薬指を第二関節辺りまで挿入し、恥骨裏側のざらざらした部分を強く擦りあげた。 「ひぃぃぃぃぃ~~~!!そこはやめてぇぇぇぇぇ~~~~~~~~~~!!」 「ふふふ……ここ気持ちいいんだろう?もっと擦って欲しいって言えよ」 「そ、そんなこと言えません」 「ふん、強情だなあ」 車野山は激しく擦り続けた。 「あっ、あっ、あっ、出そう、出そう、何か出そう!!」 何かが迸るような予感がありさを襲った。 尿意に似ているが放尿前の感覚とは違うし、愛液が溢れる感覚とも異なる。 次の瞬間、亀裂からおびただしい液体が噴出した。 BACK/NEXT |
 野々宮ありさ |
自作小説トップ
トップページ