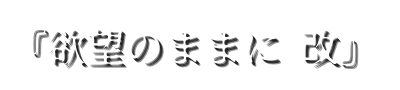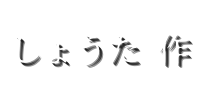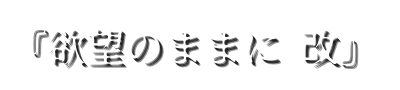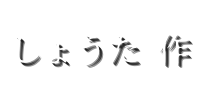7.
「淫乱じゃない、感じてない、濡らしていない。じゃあ、これは汗なんだな?」
「……」
美月は肯定も否定もせず黙ったままだ。
「わかった、こんなに愛撫しても好きな女が感じてくれない、濡れてくれないなんて、男にとってこれほどの屈辱はない……。どうやら、僕の負けらしい。もし、僕の負けが確信できれば、きっぱりと君を諦めるし、もう二度と君に近づかない。もちろん、ここまでした償いはする。退職金、慰謝料含めて、五十万、いや、百万出そう。どうだ、いい条件だろう?」
美月がゆっくり顔をあげた。目を合わさないし口も開かないが、その顔には安堵感が漂っているように見える。
「あ、もし、裁判沙汰にするならば、それでもいいよ。でも、このことは世間に公にされることは間違いないだろうね。君も知ってのとおり、僕の顔は地元では知れ渡っているからね。だから、僕だけでなく君だって、世間に好奇な目で見られるだろう。もちろん、ご主人にも、お子さんにも影響が及ぶことになるだろうね。そんな状況に耐えながら、僕とお金と時間がかかる裁判を闘っていくか、それとも、今回のことは君の胸の内に締まっておいて、百万円を謝罪金としてもらって、ここから去っていくか、どうするね?」
口を閉ざしている美月に向って言葉をつづける。
「あぁ、この条件を受けてくれないのならば、百万円の話は無しだ。君には悪いと思うけど、僕が満足するまで、君の肉体を好きにさせてもらうよ」
「そ、そんな……」
ようやく美月が弱弱しい声をだした。
「どっちが君の今後の人生によいか? 頭の良い君ならわかるよね?」
「……わ、か……りました」
「わかったって、どっちが?」
「……なかったことにします」
「なかったということは、今回のことを公にしないと受け取っていいんだね」
「はい……」
拘束しているので、まともな抵抗ができない美月だから、こんな回りくどいことをせずに一気にパンストを引き裂いて、ショーツを脱がして犯せばいいと思うかもしれないが、それでは、ただの強姦魔と一緒であり、やはりリスクが高い。
そこで、美月がお金で動く女かどうかということを確かめたかった。
美月は百万円で手を打つことを了承したので、金でどうにでもなりそうだということがわかった。
つまり、この後、美月を犯しても金額さえ積めば、彼女の口を閉ざすことができそうだと予測することができる。
これで、精神的に随分と楽になった。
「さすが、聡明な君だ。懸命な選択してくれて、嬉しいよ。だが、拘束を解く前に、確かめさせてもらうよ」
「えっ!? それはどういう意味ですか?」
「だから、さっき言ったよね。僕の負けを確信したいって。だから、君が濡れていないか、感じていなかったのか、確かめるんだよ」
「そ、それは……」
「何を迷っているんだ、濡れていないのなら何も心配することはない。ただ、確認するだけで、触らないんだから、問題は全くないだろう」
「……」
美月は視線を落とし、唇を噛みしめ黙った。
それもそうだろう、何しろ、パンスト越しに触れてわかるほど、濡らしているんだ。確実にショーツのクロッチ部は淫らな粘液で汚れているはずだ。そんな状態になっていることを美月自身が気づいていないことなどありえない。
そうわかっていて、百万円という餌をチラつかせて質問したのだ。
もちろん、条件つきだ。
犯すのは諦めて、濡れたかどうかを確認したいとだけいっている。パンティを脱がすとはいっていない。いや、当然、生の膣を拝見するつもりだが、それでも、百万円という金額は美月にとって無視できない額だと思う。なにしろ、彼女の旦那の収入はたいしたことないらしいし、家を建てた借金の返済で四苦八苦しているということも知っている。
だから彼女はフルタイムで働いているのだ。
美月の両膝に手をおいた。
「いやっ」
美月が膝を割らせないよう太腿をぴったりと閉じた。
「どうした? なんで、確認させてくれないんだ……まさか、本当はおま○こぐちょぐちょに濡らしているなんてことはないよね?」
「濡らしてなんかいません!」
「だったら、抵抗する必要はないじゃないか? 濡れていなかったら、それ以上のことはしないし、直ぐに手枷をとって、そこの金庫から百万円を渡すよ。それで、全ては終わりだ……だから、いいね」
膝頭を掴み、力強く左右に開いた。
「やっ、やめてっ」
両腕に美月の太腿の抵抗を強く感じる。膝から手をどかしたら、直ぐに無駄な肉のついていない腿が閉じられてしまいそうなほど力がこもっている。
これでは、確認できない。
「おい、おい、どうしてそんなに抵抗するのかな? 別に濡れていなければ隠す必要なんかないだろう? んっ、それとも、やっぱり、おま○こヌルヌルになっちゃった? だから、見られたくないのかな?」
「ち、違います!」
「だったら、大人しく見せなさい! これ以上、拒否するならば、さっきの話はご破算だ! 訴えるなり、なんなりしてもいい! そのかわり僕が満足するまで徹底的に君の身体を味あわせてもらうよ!」
わざと怒鳴り、上着のポケットから拘束用のビニールテープを取り出した。
「もぉ、いいよ。これから好きにさせてもうけど、君は抵抗するだろう。だから、悪いけど、これで両足も拘束させてもらうからね」
「や、やめて、そんなことしないで」
「だったら、大人しくするか! 拘束されて、犯されるよりも、見せるだけで終わった方がいいだろう!」
「……わ、わかりました、でも……」
「でも、なんだい?」
「見るだけで、それ以上は何もしないと約束してください」
「あぁ、触らないよ……」
もちろん、何もしないわけがない。
美月の膣が愛液で濡れていることは明らかだが、仮に乾いた膣であっても、ずっと憧れていた美しい人妻の猥らな性器を目にしてしまったら、何もせずに終わることはできるはずがない。
しかし、そんなことを馬鹿正直には言えば、間違いなく美月は見せることを強く拒むに決まっている。
力づくで美月の熟れた膣肉を拝むことはできるが、抵抗は少ないに越したことはない。
「じゃあ、力を抜いて」
手のひらを締まった内腿にあて、ほっそりとした太腿を左右に開きパンストに包まれた股間を露にした。
ライトベージュのパンストの中心部に延びる太い継ぎ目の線、その向こう側の薄紫のショーツの中心部が変色しているのが目に入り、思わず顔が綻んでしまう。
「もぅ、いいですか……」
美月が消え入りそうな声で訊いてきた。
「いや、これではわからないな……パンストが邪魔でよく見えない。ちょっと、パンストを破らせてもらうよ」
「や、破らないで……」
「破らないで、ちゃんと脱がせてくれというのかい? 大丈夫だ、君も知ってのとおり、倉庫には山ほど在庫がある。確認が終わったら、好きなものを履いて帰るといい。だから、破らせてもらうよ。いいね、騒いだら確認だけでは済まなくなくるからね」
冷たい声で美月を脅しパンストの中心部を掴んで力強く左右に引っぱると、パンストは乾いた音をたててパンティのクロッチ部を中心に円く裂けた。
パンスト越しでもわかったが、ライトパープルのパンティの中心は変色している。美月の膣から愛液が溢れていることは明らかだ。
「おい、おい、すごいな。パンティ、グチョグチョじゃないか」
「やっ、み、見ないでぇ……」
美月の頬が忽ち赤く染まった。
「ほんとにこれが汗か? こんなにグチョグチョになるまでパンティ濡れているから、とても汗には思えないなぁ」
「あ、汗です。汗にきまってます! もう、いいですよね。早く、帰してください!」
「あっ! シミが広がった!」
「やぁ、見ないでぇ」
嘘ではない、触れてもいないのにクロッチのシミがじわっと広がったのだ。それに、よく見ると変色した部分から透明な液がにじみ出ている。
いやらしいことを言われて興奮しているのか? 見られて興奮しているのか? いや、その両方に性感が昂っているのかもしれないが、なんにしろ美月の肉体に快楽の波がうねっているのは間違いない。
「もう認めなよ、僕にこうされて興奮してるって」
「ち、違う、そんなことありません」
「君も、なかなか、頑固だね。感じているって認めれば、拘束も解くし、優しくするんだけどな……。まぁ、いいさ、この染みの正体は何であるか、直接、美月のおま○こ見させてもらうから」
「や、ダメッ、ダメです。そ、それだけは許してください」
美月は今にも泣きだしそうな必死の形相で身体を捻り股を閉じようとしたが、股の間においた男の膝がそうはさせない。
両膝で美月の股をさらに押し開き、濡れたクロッチを摘んで捻り一気に横にずらした。
「いやぁぁっ!」
「おぉぉっ!」
ついに念願の人妻の膣肉を目にし、たまらず歓喜の声をあげた。
「やっ、み、見ないで」
女性の性器を見ないでと言われても、見たいのが男というものだ。まして、憧れの女性の膣ならなおさらだ。
美月の割れ目を食い入るように見つめる。
肉ビラは若い娘と違い、黒ずんでいて、お世辞にも綺麗とはいえない。だが、かえって、夫をふくめ、何人もの男が舐め、弄り、肉棒で摩擦され黒ずんでしまった人妻の肉ビラの方がいやらしくていい。
貝が合わさったように閉じてはいるが、はっきりと汗とは違う粘度の濃い液体で濡れている使い込まれた肉ビラに、早くその味を試してみたいといわんばかりに肉棒がビクビクと跳ね上がる。
「す、すごい……すごいよ、美月ちゃんのおま○こ。真黒だ!」
「やっ、そんな……あぁ、やだぁ」
美月が力なく言った瞬間、亀裂から蜂蜜のようにトロリとした一筋の粘液が流れ、ソファに糸を引きながら垂れおちた。
過去の恋人たちの中にも濡れやすい女はいたが、こんな粘っこい蜜が滴り落ちるのを見たのは初めてだった。
タダでさえ悶々としているに、その衝撃的な光景がさらに淫猥な感情を昂らせる。
「あぁ、ほんとに、いやらしいおま○こだ。見ているだけなのに、エッチな蜜が流れてきたよ」
美月の瞳と淫裂と交互に視線を移しながら言う。
「やっ、そ、そんなことありません」
「まだ、これが汗だっていうのかい? この粘り、どう見ても愛液にしか見えないんだけど」
「ち、ちがう……ちがいます」
「ほほぉ、まだ否定するんだね」
「もぉ、いいでしょ。見るだけだって言いましたよね。約束は守りました。だから、もぉ……」
「ふぅ……」
深い息を漏らし、クロッチに張り付いたねっとりとした液体を指ですくい匂いを嗅いだ。
「いやらしい匂いがする」
「や、やめて」
「これが汗か?」
美月の顔に濡れた指を近づけると、美月は指から逃れようと横を向いた。
「どうした、匂いを確認してくれなきゃわからないじゃないか?」
美月の鼻孔に指を持っていく。
「いやっ、いやです、ん、うっ、いやっ」
匂いを嗅ぐのを嫌がった美月の口内に指を挿入すると、美月は顔を振ってその指を吐き出した。
「どう、愛液の味がするだろう?」
「そんなの知りません!」
「どれっ」
再び、クロッチに張り付いている汁を指につけ、自分の舌で舐めた。
「やっぱり、汗じゃない……ま○汁の味だ」
「ち、ちがう……」
「わかった……」
力なく否定する美月を見つめながら、スーツの上着を脱ぎ床に落し、つづけてネクタイを外し、スーツの上に放った。
そして、センターテーブルからデジタルカメラをとり電源をいれ無残な姿になった美月にレンズを向けた。
「やっ、やめてください!」
パシャッ!
パシャッ!
写真を撮られることに非難を浴びせる美月を無視して、美しい人妻の無残な姿、濡れた割れ目をSDカードにおさめた。
「写真はやめてください! かっ、確認するだけって、いったじゃないですか!」
「あぁ、そうだよ。確認したよ、やっぱりま○汁だったって」
「くっ……」
早速、撮った画像を背面ディスプレイで確認すると、汗で蒸れて肌にはりついた恥毛の艶、粘液にまみれたいやらしい割れ目の輝きがくっきりと写し出された。
最高の画質で撮れた卑猥な画像にほくそ笑みながら、美月の眼のさきへディスプレイを向ける。
「やっ」
美月は瞳を閉じて、濡れた亀裂を見ることを拒んだ。
「おい、おい、せっかく綺麗に撮れたんだから、ちゃんと見てくれきゃ困るな」
瞼も口も開かないが、頬や耳たぶが真っ赤に染まっていることから、美月が強烈な羞恥心に襲われていることがわかる。
「なんで、見てくれない? 自分のおま○こなんだから、どうってことないだろう? 早く、見てくれよ。これがま○汁なのか、汗なのか、ちゃんと、その二つの目で確認してくれよ」
「いやです!」
「ふぅっ。君もなかなか強情だねぇ……こんなにま○汁垂れ流しているくせに」
「ち、違う……」
「まぁ、いいさ」
堂々めぐりに嫌気がさし、冷たく言い放って、美月から離れた。
「約束は守りました。だから、もぉ……」
「もぉ、なんだって? 君は約束を守ってはいないぞ」
「えっ!」
目を丸くした美月を一瞥して、センターテーブルの下から予め用意しておいたスケルトンローターとバイブレーターを両手に持った。
「これがなんだか、わかるよな?」
「や、やだっ、何もしないって言ったじゃないですか」
美月が怯えたような瞳を向けた。
「触らないとは言ったが、何もしないとは言っていないよ」
「そ、そんな……酷い」
「使ったこと、あるか?」
「そんなの使ったことありません!」
きっぱりと否定した美月の言葉が本当かどうかはわからないが、そんなことはどうでもよい。乳房だけしか愛撫していないのに、亀裂をぐっちょりと濡らしている美月が大人の玩具によって、どう反応するのか? そっちの方が早く見てみたい。
最初は何度も使ったことのあるローターからと決めていたので、迷うことなくバイブを置いてローターのコントローラー部分にあるスライド式のスイッチを滑らせた。
電気カミソリより強いモーター音をたてながら本体が小刻みに震えはじめる。
まず、手始めにとがった美月の乳首に本体をあてた。
「あっ! やんっ!」
美月の身体がピクッと跳ねる。
「はは、感じやすいんだね、乳首でこれだ。こいつをクリちゃんにあてたら、どうなるかな?」
「や、お、お願い……、ゆ、許して、許してください」
眉をハの字に曲げながら美月は懇願する。
「そんなに、おびえなくてもいい……こいつはオンナを感じさせるための道具なんだから」
「や、いや、いやです。ちゃんと、見せたじゃないですか……、何もしないって、何もしないって約束したじゃないですか」
「だから、何もしないとは言ってないぞ。君のおま○こ、手で触らないとは言ったが、おもちゃで触れるのは約束を破ったことにはならない。それに舌で舐めることもね」
「ひ、ひどい……」
「ひどいのはどっちだ! 嘘をついたのは君の方だ! 感じていない、ま○汁を汗だなんて嘘をついたのは君だろう?」
「う、嘘じゃありません!」
「ほら、また嘘を吐く!」
「うっ、ぅっ」
「もう、君の嘘は聞き飽きたよ。嘘さえつかなければ、解放してやったもの……だから、こいつで認めさせてやるのさ」
「う、嘘じゃ、なぁ、あっ、あぅっ!」
ローターをクリトリスへあてると、美月は眉根を寄せ、腰をぴくりと浮かして甘く呻いた。
「まだ、俺を騙すつもりか! えっ!」
「あぁっ、ひ、ひ、あっ、やっ、やぁ、そんな、やめ、やめてぇ! あぁっ、いやっ、あっ、あぁぁっ」
「だったら、認めるか!」
細かい振動から逃れようと美月は腰を捩るがクリトリスからローターは離れない。
「あぁ、ダメッ、やっ、ひっ、あぁっ、ダメッ、おっ、お願い、お願いですからやめてぇぇ」
「質問の答えになっていないぞ!」
一気にローターの震動を最強にすると、美月は小顔をのけぞらし腰をくねらせ呻きだした。
「あ、あっ、ダメッ、ああぁぁぁぁぁっ! こんなの、あっ、やっ、ひっ、やめ、てぇっっ!」
亀裂からとめどなく粘液が流れ、乳房には鳥肌が浮かんでる。やはり、敏感な豆に与えられる震動はかなり感じるらしい。
そんな美月の猥らな反応が欲情を一気に限界へ持ち上げた。
もぉ、冷静ではいられない。
クリトリスにあてたままのローターを横にずらしたクロッチで覆い、ローター地獄で身体をくねらす美月を見ながら、ベルトを外し、スラックスをボクサーブリーフごとずり下ろし、極限状態の肉棒をあらわにした。
一週間、禁欲した肉棒は腹に張り付きそうなほど角度を保ち、ピクピクと揺れている。ねっとりとした液体にまみれた亀頭はパンパンに膨らみ、青筋がくっきりと浮き上がっている陰茎の太さは自分でも驚くほど元気がいい。
「ひゃっ、あぁっ、そんな、なにも、あぁっ……なにも、しないって、うっ、やっ、やめて、やめて……くだっ、あぁ、ダメっ、だ、だれかぁぁ……」
悶え続ける美月がそそり立つ肉棒を大きな瞳で見て、怯えたような声をあげ、どこにもいないヒーローに救いを求めた。
そんな、クリトリスへの刺激に苦しそうな表情をしながら、なやましい声をあげている美月の胸の上に膝を立てて跨った。
「やっ、あっ、いやっ!」
美月が顔を横にそむけた。間近にきた肉棒から逃れようとしているのだろうが、無駄なことだ。
「ほらっ、舐めろ……舐めるんだよ……」
上半身を前方に軽く倒し、肉棒を右手で握り、その先端をピンク色の頬に擦りつける。
「やっ、いっ、やっ」
瞼を固く閉じて巨大な肉の塊を拒否する美月の頬が透明な液体で汚れていく。
「舐めろ……舐めろって」
横を向いた美月の頭を掴み、強引に正面へ向け、腰を突き出しピンク色のルージュに彩られた唇に亀頭の先端部を押しつける。
「うっ、うっ、う~んっ……」
美月は、眉を顰めて、肉棒の挿入を拒もうと頑なに唇を結んだ。だが、それも僅か数秒の抵抗だった。クリトリスから湧きあがる快楽に耐えられないのだろう、すぐにその唇を開き、激しい息が濡れた亀頭に吹きかかる。
今がチャンスだと、腰を突き出し肉棒を口内にぶちこもうとすると、
「あぁ、あっ、ゆ、ゆる、して……やだっ、だめっ、うっ、あっ、ひっ、ひっ、やっ、だっ、あぁ、あぁ、ひっ、ひっ、いぃ、いやぁぁぁぁぁっ」
美月は背をのけぞらせ真っ白な首を露にし甲高い声をあげた。
どうやら、美月は果てたらしい。しかし、まだローターはクリトリスを刺激しており快楽地獄はつづいている。快楽の余韻に浸っていることはできない美月はすぐに覚醒した。
「あ、あぁ、あぁぁ、と、とめ、て、やっ、が、いいっ、いぃ、し、し、しんじゃ、し、死んじゃうっ!」
口からよだれを垂れ流し絶叫し、全身を大きく痙攣させつつげる美月の様子に驚き、あわてて、上半身をひねり、ショーツから伸びているローターの白いコードをひっぱった。 震動したままのローターがするりと抜けると、弓なりになっていた美月の背中がソファにおちた。
大きく呼吸をしながら身体をピクピクと痙攣させている美月を見ながら、ローターのスイッチをきり、彼女に声をかけた。
「みつき、美月……」
荒い息を吐きつづけたまま美月は瞼を開き、虚ろな目で俺を見つめてきた。
「いったんだね?」
「……ひ、ひどい」
美月は消え入りそうな声をだし、横を向いた。
そんな余韻に浸っている美月をそっとしておいてあげればよいのだろうが、己の情欲が満たされていない俺は美月の身体を起こして、気だるそうな美月の口元に肉棒を近づけた。
「さぁ、今度は僕の番だ。何をするのかわかっているよな……」
「……やっ」
「それは通用しないよ、ここまできたんだ。僕が満足するまで君を解放しないことくらいはわかるだろう? 舐めるのがいやなら、おま○こにぶちこませてもらうけど、もしかしたら、我慢できなくて中に出してしまうかもしれないがね……。いや、それとも、肉棒をぶちこんでほしいか?」
「ひ、ひどい……」
「迷っている時間はないぞ、美月……もぉ、俺は限界だ。今すぐしゃぶらなければ、おま○こでいかせてもらうから」
美月は頭を軽く左右にふってから、亀頭を唇で包み込んだ。
「うっ、ううっ」
生暖かい感触が亀頭に伝わり思わず喉から声が出てしまう。
グロテスクな肉の塊を瞳を閉じ、頬をへこませて小さな口で咥える美月をじっと眺めた。憧れの人妻の卑猥な光景に全身に震えが走る。
見えないところでオンナの舌が亀頭を擽る。その舌さばきは緩慢だが、それでも敏感な亀頭に快感の波が渦巻き、吐く息も荒くなる。
素晴らしい眺めからいったん目を離し、膝を曲げて腰を少しおとし、センターテーブルのうえにおいたデジタルカメラをとった。そして、瞳を閉じたままで、醒めたフェラチオをつづける美月にレンズを向け、シャッターをきった。
ピピッという電子音とともにフラッシュがたかれ、美月が瞼をひらき、レンズを見つめ慌てたように肉棒からチュポッと唇を離した。
「やっ、写真は……写真は撮らないで……」
「大丈夫だ……この写真をネタに関係を強要したりはしないし、他人に見せたりすることもない。ただ、個人で楽しむだけだ」
「でも、写真は……」
「いいか、僕は約束は守る男だ。君は僕に嘘をついたけど、百万の話もまだ有効だ。だから、何も心配することはない」
「でも……」
「この話はこれで終わりだ。美月は俺を信用するしかない。早く、しゃぶれ」
泣きそうな瞳を向ける美月に命令すると、再度、肉棒が美月の温かい口の中におさまった。
相変わらず舌の動きに熱がこもっていないことにイライラしながら、フェラチォシーンをデジカメにおさめていく。
「どうした? そんなフェラじゃ、永遠に俺をイかせることはできないぞ。それとも、おま○こにぶちこんでほしくて、たまらないないか」
美月は肉棒を銜えたまま首を横に振る。
「だったら、もっと、真剣にやるんだな……」
ローターで狂ったように淫らな姿を見せた美月だが、まだ挿入を拒んでいる。美月の精神は崩壊していないことがうかがえる、だが、焦る必要はない。挿入すると言った途端、美月の舌の動きが変わった。
力のこもった舌が亀頭を這いまわる。唇をすぼめ首をスライドさせ亀頭を刺激する。これぞ、期待していた人妻のテクニックだ。
美しい人妻のフェラ顔、時折、奏でるいやらしい唾液音、そして直接伝わる亀頭への刺激にたちまち射精感が湧き上がってくる。
が、堪えた。
射精したいのに堪える? 矛盾しているかもしれないが、男というものはそういうものではないのだろうか? なにしろ、女性と違い、男の快楽はいたって単純、一瞬だ。だから、その快楽の頂点に上り詰める寸前の快感を少しでも長く味わっていたいのから射精を我慢したいと思い耐えるのだろう。
しかし、そんな思いをあざ笑うかのように美しい人妻のいやらしい舌が容赦なく亀頭を襲う。
括約筋に力を入れるが、これ以上は耐えられそうもない。一気に精液をぶちまけたいとの強烈な誘惑にいざなわれる。
限界だ。出すしかない。
出そうと決めたときは、我慢しないほうがよい。その方が快楽が強烈だし精液を吐き出す勢いもある。
美月の後頭部に手をかけ、射精に向けて括約筋から力をぬいたとたん、痺れるような快感が襲ってきた。
「うっ、ううっ、い、いきそうだっ、うっ、だ、出すぞ、出すからなっ、うっ、うっ」
肉棒の根元が脈打ったと同時に腰をひいた。チュポッといやらしい音と共に肉棒が美月の口唇から吐き出される。美月が目を開き、えっ? という表情で俺をみあげた。
その瞬間、肉棒に力強い脈動を感じ、亀頭が膨りあがり尿道口からブシュッと鋭い音をたてて白濁液が美月をめがけて噴出した。
一発目の噴射は勢いよすぎであわてて顔をそむけようとする美月の頭上を通り越し、壁にぶちあたる。二度目の噴射は美月の髪をかすめた。美月の顔面を汚したいと願う俺は慌てて美月の頭を解放し角度のついた肉棒をつまみ、先端を美月の顔面に向けた。ついに噴出する精液が美月の額にかかった。
「きゃっ」
既に遅いが、美月が顔射を避けようと、顔をそむけた。
いったい、この爆発はどれだけつづくのだろう、と自分でも驚くほど肉棒はドクッ、ドクッと力強く脈動し精液をとばしつづけ、美月のピンク色の頬を汚していく。
その素晴らしい光景に膝を震わせながら、この快感が永遠につづけばいいと思った。
が、さすがにそうはいかない。脈動がとまり、最後の精液が美月の膝にポトリと垂れ落ちた。
(あぁ、やった、ついにやってしまった……)
顔射という一つ目の願望を成就したことに全身が震えるほど感激しながら、せっかくかかったザーメンに触れないよう美月の顔を上に向かせた。
最後の一滴まで美貌の正面に精液をかけたかったが、額から瞼を通り鼻筋にかけてしっかりととろみの強い精液が張り付いているので、まぁ満足だ。
「こ、こんなの、ひ、ひどい……」
「今、拭いてやる。だから、そのまま顔をあげとけよ。それと、絶対目をあけるなよ。ザーメンが目に入ったら失明するかもしれないからな」
失明とは大げさだが、ザーメンが目に入るとかなり沁み、結膜炎になる場合もあるらしい。
だが、あえて大げさに言った。
顔射最後の仕上げとして、精液まみれになった美貌を記録に残すためだ。
「いいか、じっとしてろよ……」
そう言いながら、デジタルカメラをとり、ザーメンまみれの美月の顔にレンズをあわせ、シャッターをおろした。
前頁/次頁 |