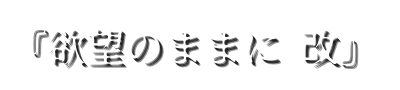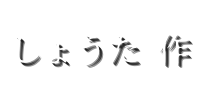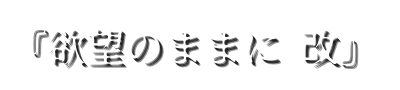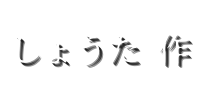6.
「いやっ! やめてっ! やめてくださいっ!」
両手を拘束された美月は激しく身体を捩った。だが、痩せた女の力では、鍛えられた男の身体を跳ね除けることなどできはしない。まして、美月は俯伏せだ、更に力を出せないだろう。
そんな無駄な抵抗をする美月の背中に胸を重ね、乱れる髪から見える耳元へ口を寄せた。
「暴れて無駄だよ」
「何を、何をしたんですか! やっ、何これっ! 外して! 外してください!」
「き、君が悪いんだぞ……君さえ僕を受け入れていれば、こうする必要はなかったんだからな」
「受け入れる? ど、どういう意味ですか?」
「決まっているだろう、受け入れるってことは、セックスすることだよ」
「セ、セッ……って、そ、そんな……勝手なこと許されるわけないでしょ!」
「許してくれないから、こうしたんだよ」
「ひ、酷いわ……そんなの絶対許せない!」
美月の背後に乗っているので、その表情はわからないが、耳が真っ赤に染まっていることから、美月の怒りの感情がかなり湧き上がっていると伺える。
美月の立場を思えばそれも当然なことだろうが、俺はその怒りに動じないほどこの美しい人妻に欲情している。
「放して! 放してください! こ、こんなこと許されることだと思っているんですか!」
美月はどうにもならない身体を左右前後に揺すりながら、怒りに震える声をあげた。
当然、俺は応えない。
正しいのは美月だから、応えたところで、言葉では勝てるはずがないからだ。
美月の華奢な肩に手をかけスリムな女の身体をくるりと反転させた。
「ひゃっ!」
目を円くしながら驚きの声をあげた美月の上に素早く覆いかぶさり、両手で美月の頬を押さえ唇を奪った。
「うぅっ、うぅっ」
美月がくぐもった声をあげ、首を激しく振った。だが、両頬をしっかりと抑えているので、まともに首を振れずにいる。当然、俺の唇から逃れることはできない。
しっかりと唇を合わせたまま、舌を突き出し尖らせた。女の唇を割って口の中を侵そうと舌をねじ込んでいくが、美月は唇を硬く閉ざしその侵入を許してくれない。
激しい抵抗を打ち負かそうと、何度も挑戦したが、美月は頑として唇を開くれない。
そんな美月の強い意志を感じ、カーッ! と頭に血が上ってきた。
美月の整った鼻をつまんで、無理やり口を開かせようかと思い、左の頬から右手を離した。
その瞬間、美月の顔が横に動き、唇が離れた。
「そんなに、いやか!」
「あ、あたりまえです!」
美月が顔を叛けたまま怒鳴った。
(そんなに、いやなのか……)
美月の激しい怒りにズキンッと胸に痛みが走った。
拒否されることは、予測していたが、ここまで激しい怒りをぶつけてくるのは想像していなかったからだ。
(それほど、嫌われているのか……)
こんな思いは初めてだった。もちろん、今までは女性たいして紳士的に接してきたから、嫌われることなどなかったのだろうが……。
ショックで、気持ちが萎えてきそうだ。
だが、既にここまでやったのだ。
気持ちに負けて、仮にここで止めたとしても、美月を拘束して、強引に唇を奪ったという事実を消すことはできない。
それに、こんなことがあったのだから、美月が会社を辞めてしまうことは明らかだ。辞めてしまったら、この美しい人妻の身体を味わうことは、限りなく不可能になってしまう。
横を向いたまま、一点を見つめる美月をじっと見つめた。
(いいオンナだ……)
見れば見るほど、美月の肉体だけでなく心まで自分の手中にしたいとの気持ちが募ってくる。だが、他人の妻であり家庭を持つ美月の全てを手に入れることは限りなく不可能なことだろう。美月が人妻でなければ、独身の時に出逢っていれば……とやるせない思いが湧きあがってくる。
しかし、そんな感情に浸っている場合ではない。
時は一刻一刻と過ぎていく。
美月の肉体を楽しめる時間はあと三時間くらいしかない。
今は深い口付けは諦めよう。またチャンスもあるだろう。気を取り直して先に進もう。
そう思って濃紺の制服の上着のボタンに指をかけた。
「もう、いい加減にしてください……」
怒りの眼差しを向け冷たく言い放つ美月の声に、戻りかけた強い気持ちが再び萎えていくのを感じながらも、ボタンを全て外し上着を左右に開いた。
「いい加減にしてよね!」
「うるさいっ! それが目上に使う言葉かっ!」
美月の怒鳴る声に、思わず怒鳴り返した。
萎えかけていた気持ちが、一気に湧き上がった怒りの感情に消されていく。
白いブラースの胸倉を逆手に掴み、力強く左右に開いた。ブチッ、ブチッとブラウスのボタンが弾け跳ぶ。ほぼ、同時に美月が叫んだ。
「いやぁっっっっ!」
甲高いオンナの叫び声が鼓膜を激しく震わせる。
「うるさいって、いっているだろっ!」
美月の顔にかむって渾身の力を込めて拳を振り下ろした。
「やっ!」
美月が目を閉じ、小さな悲鳴をあげた後、ドスッという鈍い音が耳にはいった。拳は美月の美貌の横のソファの座面にのめりこんでいる。
感情的になってしまったが、美月を殴るつもりなど、毛頭もなかった。ただ、あまりにも激しく暴れる美月に恐れを抱かせればよかったのだ。
美月の瞳に怯えの色が浮かんでいる。
恐怖を与えることには成功した。
しかし、ここからが肝心だ、美月を感じさせなければならない。
薄紫のブラジャーに手をかけた。
「お、お願い……お願いしますから、やめて……社長、今なら、今なら……」
声を震わせ懇願する美月を無視しブラジャーのカップを一気に上にずりあげた。
「やっ……」
弱々しい声をあげて美月が身体を捩ると、露になった小ぶりな乳房がプルンと波打った。
「あぁ……」
ずっと想像していた二つの膨らみをついに見れた。何度も視姦したオンナの膨らみは想像していた通り、小ぶりな乳房だった。だが、小ぶりとはいえ、その感触を楽しむだけの膨らみは充分にある。焦げ茶色の乳輪も適度な広さで細かい粒も少ない。そして、乳輪の中央にある乳首がその存在を誇示するかのように起立している。焦げ茶色に染まった乳首は夫や夫と出会う前の彼氏達に幾度となく弄られ舐められてきたのであろう。
感動と興奮で身震いがするほどいやらしい乳首だ。
「やっ、お願い、許して、お願い、本当にお願いですから……」
瞳の奥に怯えを浮かべながら弱々しいメスを見せる美月に、スラックスを突き破らんばかりに膨れ上がった肉棒がズキズキと脈打つ。
憧れていた人妻の肉体を意のままにできる状況に、精液を限界近くまで溜め込んでいる肉棒、そして、強姦という普通の人間ならば、絶対にできぬ行為をしていることが、重なり合っているのだろうか、こんなに興奮を感じてたのは記憶にない。
鼻と口から漏れる激しい吐息、口唇から零れそうなほど溜まる唾液、まるで、飢えた猛獣のようだ。
獣のように、一気に乳房に食らいつきたいとの誘惑にかられるほど、興奮している。
美味しそうな獲物を前に、逸る気持ちを必死にねじ伏せ、ゴクリと喉を鳴らして、いやらしい二つの乳房に両手を重ねた。
「あっ、やっ、触らないで、あっ、やっ、め、てぇ~」
二つの乳房を両の手で揉みだすと美月が眉をハの字にし泣きそうな声で嫌がった。しかし、当然ながら嫌がられても手を止めるつもりはない。乳房に乗せた手に力を込めた。
数々の男たちに揉み込まれてきた三十路の人妻の乳房はマシュマロのように柔らかかった。十代後半から二十代半ばくらいの乳房のように揉み込む手を弾き返すような反発はないが、それでも、小ぶりな乳房はしっかりと十本の指を弾き返しているのがわかる。
「や、お願い、お願いですから、もう、や、やめてください……」
「やめてくださいだって? まだ始まったばかりなのに、やめられるわけがないだろう。それになんだこれは! なんで、こんなに乳首が硬くなっているんだ!」
乳首の先端を中指の腹で軽く擦った。
「あっ、ダメッ!」
「何がダメなんだ。こんなに硬くなってるってことは感じているからだろう?」
「ち、違います……しゃ、しゃ、ちょうがぁぁ、うっ、やっ、やめてぇ~」
頂きの先端を円を描くように擦ると美月が身体をくねらせ甘みを帯びた声をあげた。
(感じているんだ……)
それを確かめるために、二つの乳首を二本の指で摘みコリコリと左右に動かすと、美月は眉を寄せ、唇を結び、何かに耐えているような悩ましい表情を見せた。
(間違いない、感じている……)
美月が感じていることが、嬉しくて思わず笑みが零れる。
「どうだ、気持ちいいだろう?」
「き、気もちよくなんか、あり、うっ……ません……」
「だったら、どうしてこんに乳首を硬くしているんだ?」
乳首を弄りながら、美月に尋ねる。
「弄るから……」
「なに、よく聞こえないなぁ、なんだって?」
「社長が、弄るからです!」
「ほほぉ、僕が触るから乳首を硬くしたというのか……」
「そ、そうです……だ、だから、あっ、もぉ、や、や、止めてください」
「嘘をついたらいけないなぁ、君の乳首は僕が触る前から硬くなったよ……本当はこうして拘束されて犯されていることに興奮しているんじゃないのか?」
「そ、そんなこと、あっ……ありません」
「感じているだろ、気持ちいいって素直に認めちゃえよ、いやらしい美月ちゃん」
「もぉ、いやっ! こ、こんな、こんなことして、ただで済むと思っているんですか!」
美月は眉を吊り上げて怒鳴った。その顔を真っ赤にそまり、瞳には力強さが漲っているのが見てとれる。
間接的な暴力により弱々しくなった美月に、もう、さした抵抗はないだろう思っていただけに、美月の敵意ある目に驚きを覚えた。
それほど、嫌なのか……。
いや、違うかもしれない。
ここまで怒るのも、逆に考えれば、美月は、これ以上乳首に触られつづけたら、自分を制御できることができなくなってしまうと思ったからではないか?
だから、消えかかってた感情が復活し爆発したのではないか?
その真意は美月でなければわからないが、試してみれば答えはでる。
「おい、おい、美月ちゃぁーん。君は、まだ自分の立場ってものがわかっていないようだね。何度も言うけど、僕は既に覚悟を決めているんだよ。君とセックスできるなら、全てを投げ出したっていいってね……だから、大声を出すだけ無駄だ。もう、諦めて言うことを聞くんだよ!」
「そんな、勝手な……勝手すぎるわ……」
「そんなことだってわかっている。けど、仕方がないんだ。君さえ、君さえ、僕の前に現れなかったら、こんな気持ちにはならなかった……いいか、もう君にはどうすることもできないんだから、大人しくしろ!」
「く、狂ってる、狂ってるわ……」
「そうだ……狂っている。狂っているんだよ、僕は! だから、騒いだら何をするかわからない……いいな、騒ぐなよ」
そう脅しをかけて、徐に乳首に吸い付いた。
素裸から漂う甘い石鹸の香りを吸い込みがら、乳を搾るかのように乳房を掴み、隆起を盛り上げ、突き出した乳首にレロレロと舌を這わせていく。
のの字を描くように舌を回したり、舌の先で突いたり、唇に含み吸ったり、と夢中になって舌を弾き返すほどの硬さを持った左右の乳首を唾液で汚していく。
「お、お願い、や、やめてっ……やっぱりダメっ……こんなの、こんなの卑怯です」
チュパッと音を立てて、乳首から口を離した。
唾液によってテカテカに輝く乳輪が、いっそういやらしさを引き出している。
「卑怯……そうだね。それも君の言うとおりだ」
「お願い、私の知ってる社長はそんな卑怯な方ではないはずです。お願いします、どうか、どうか許してください。お願い、今すぐ変なものを外してください……」
「……じゃあ、抵抗せずにやらせてくれるかい?」
「そ、それは……」
美月が視線を落とした。
「なんだ、まだ迷っているのか? もう一度訊こう。手錠を外したら、美月の同意のうえで、美月のおま○この中に僕のチンポをぶちこませてくれるんだな!」
美月の頬が忽ち朱に染まった。
卑猥な言葉を耳にした美月の脳裏に俺と交わる場面を浮かべてしまったのかもしれない。
「ちゃんと応えるんだ……」
美月は目線を泳がし、困惑の表情を浮かべた。
もちろん、答えに窮することはわかっていた。
拘束を解く解かないに関わらず、美月に俺を受け入れろと言っている。
全てを解放してほしいと願っている美月の立場にたてば、こんな理不尽な条件を呑めるはずはない。
「いつまで待たせるんだ。君だって、子供じゃないんだから、男の性がどんなものであるかわかっているだろう。男は一旦求めたら射精するまで、終わらないってことを……」
「……そんな……困らせないで……」
「やっぱり無理か……。だから、僕の望みを叶えるためにはこうするしかないのさ!」
と力強く言って、再び、尖った乳首を舌で責めはじめた。
「やっ、だめっ……」
尖った乳首を舌で転がし、あいてる乳房を手で揉みしだく。
「だめっ、お願い、やめてっ……」
必死に懇願する美月の悲しそうな声が耳にはいってくる。しかし、その嫌がる声が、かえって俺の情欲の血を騒がすことを美月は知らないだろう。
より情熱を込めて乳房への愛撫を暫らく続けていると、美月の声がだんだんと掠れてくるようになってきた。
更に執拗な愛撫を加えると、拒否の言葉に変わって、不規則な吐息が耳にはいってくるようになった。
執拗な乳房、乳首への愛撫に陥落したのだろうか?
拒否の言葉を出しても、一向に愛撫をやめないので、ついに言葉の無駄に気づいたのか?
それも、知ることはできないが、グロテスクでいやらしいオンナの下肉を確かめれば明らかになることだろう。
充分すぎるほど揉みほぐれた乳房から右手を放し、制服のスカートの裾を掴み上へとずらして柔らかいオンナの太腿の間に膝をいれた。
すると、美月は両の太腿を閉じて、膝を追い出そうと下半身をくねらせた。
しかし、太腿の奥まではいった膝を容易には追いだすことはできない。
「やっ、やめてっ……」
暫らく、黙っていた美月が切なそうな声をあげて下半身を左右に振った。
「おやっ、まだ諦めてなんいだ?」
「やっぱりダメっ、わたしには無理です。だから、お願い、もう、勘弁してください……」
腰をくねくねとさせて懇願する美月の太腿の間にある膝を立て膝の頭を股間に当てた。
「あ、やっ、ダメッ……」
美月が艶っぽい声をあげ、下半身をくねらせるのを止めた。
直接ではないが、膝頭がオンナの部分に触れているのだから、下半身を動かせば、美月自ら、敏感な箇所に刺激を与えてしまうことになるから当然のことだ。
「お願い……」
「ダメだ……」
美月に冷ややかに言い、遊んでいた手をパンスト越しの膣肉へあてた。
「やっ、ダメッ!」
美月が短く叫んで、尻を激しくくねらせるが、それも無駄なことだ。
けっして追い出すことができない男の膝によって、右手の自由を奪うことは不可能だ。
熱い股間にあてた二本の指に意識を集中させると、股間が湿っているのを感じた。パンスト越しでもわかるのだから、生の膣肉はもの凄く卑猥な状態になっていることだろう。
「なんだ、やっぱり、濡れているじゃないか……」
ワザと卑猥に言うと、美月の顔が忽ち、真っ赤に染まった。
「僕がどんなに頑張っても、君は声も出さないから、てっきり僕は君が感じていないんだと思ったよ。男にとって、自分の愛撫で女が感じてくれないほど屈辱的なことはない。だから、おま○こ触ってみて乾いているようだったら、諦めようと思ってんだが……湿っていた。感じていたんだね、嬉しいよ、美月……」
「……ち、違います、感じてなんかない」
美月は頬を朱に染めたまま、弱々しく否定した。
「ほぉ~、こんなにお○んこ湿らせてても感じていないってかっ! 嘘はつくな! もう、いい加減認めちゃえよ、感じてるって。そうすれば、もっと、楽しめるから」
中指と薬指を中心部にぐいっと食い込ませると、愛液が指についたのではと感じるくらいに濡れているのがわかる。
「美月……もう認めなさい。社長に犯されているに、おま○こから、いやらしいお汁を垂れ流してている淫乱な女だって」
「ち、違います……」
「感じてないのか?」
「感じてなんかいません」
「濡らしてないのか?」
「濡らしてません」
美月は相変わらず、視線をそらしたまま、頑として自分の肉体の状況を否定する。こんな問答をこれ以上つづけてもどうしようもないことだ。膣を濡れしているのは明らかなことであるし、どうせ、この後、美月の膣と対面することになるのだから。
しかし、その前に、もう一つ確かめたいことがあった。
犯罪を犯罪にしないために……。
前頁/次頁 |