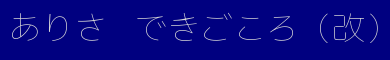 |

| 第2話 「防犯カメラにちゃんと写ってるから、知らないとは言わせないよ」 「ごめんなさい……私がやりました……」 ありさは打ちひしがれた表情で目を落としたままぽつりとつぶやいた。 「万引は今回が初めて?」 警備員はずばりと尋ねる。 ありさは俯いたまま小さくうなづいた。 「本当に初めてなの?いつもやってるんじゃないの?」 「いいえ、本当に初めてなんです……」 「で、何を盗んだの?」 「えっ……?あのぅ……シャンプーとリンスです……」 「ふ~ん……本当だね?」 「は、はい……それだけです……」 「じゃあシャンプーとリンスを出してください」 問い詰める警備員の眼光は獲物を狙う鷹のように鋭い。 彼の名前は『車野山大輔』といい33才で独身。 外見は痩せていて精悍な印象の男である。 仕事は真面目でギャンブルもしないが、人一倍好色家で周囲や状況を省みず猪突猛進で突っ走ってしまうところがあった。 前の職場でもそれを裏付ける逸話がある。 当時車野山は営業をしていたが得意先の会社に類まれな美貌の女性がいた。あいにく彼女は既婚者であったが車野山は気に留めるこ となく手練手管で彼女を口説き落とし深い仲となってしまった。やがて双方の会社で話題となってしまい、ついには車野山は会社の名 誉をきずつけたとの理由で懲戒免職となってしまった。 唯一車野山の弁護をするならば、彼は誰彼なしに手当たり次第に手を出すという訳ではなく、深く惚れ込んだ女性だけをターゲット としていた。 ありさはバッグからシャンプーとリンスを取り出し机に並べた。 「くどいようだけど、本当にこれだけだね」 「は、はい……これだけです……」 「嘘は絶対ダメだからね。後からビデオで調べりゃ分かることだし」 「はい……」 「まだあるんだろ?隠しても無駄だよ。君の顔に『まだあります』と書いてあるもの。僕の眼はごまかせないよ」 「……」 語気は穏やかだがすごい威圧感だ。 ありさの嘘を見透かしたかのように迫ってくる。 ありさは車野山の威圧感に圧倒され、ついに白状してしまった。 「す、すみません……もうひとつ盗みました……」 「ふうん、やっぱりね。最初から正直に言ってもらいたいなあ。で、何を盗んだの?出してもらおうか?」 「え?いえ、ちょっとそれは……」 恥じらいから『タンポン』と言う言葉を口にできなかったありさは顔を紅潮させ隠したタンポンを出し渋った。 「早く出しなさい」 これ以上隠し通す訳もいかない。 ありさは仕方なくタンポンをバッグから取り出した。 「なに?これ……」 分かっているのにわざと知らないふりをしているのか、それとも本当に知らないのか。 いくら男でもタンポンを知らない成人男性は珍しいだろう。 いずれにしても無視をする訳にもいかないので、ありさは小声でつぶやいた。 「タ、タンポンです……」 「タンポン?へえ?それってどこに使うの?」 「え?そんなこと……そんなこと恥かしくて言えません」 「恥かしい?恥かしいような場所に使うものなの?」 「……」 万引きは悪いことだが、だからといってそんなセクハラな質問に答える必要があるのだろうか。 ありさは沈黙した。 「言わないのか?まあいいけど。じゃあ今から警察に通報するのでその椅子に座って待ってて」 車野山はそう言いながら受話器を握った。 電話のプッシュボタンを押し始めたとき、ありさは泣き出しそうな顔で車野山の腕にすがりついた。 「警備員さん、ごめんなさい。警察に電話するのだけは許してください。もし捕まったら大学は退学処分です。どうかそれだけは勘弁 してください。謝ります!本当にごめんなさい!だからお願い、警察に通報するのだけはやめて……」 ありさは涙ぐみながら何度も詫びた。 車野山は受話器を元の位置に戻してありさに語り掛けた。 「うん、分かった。初めてのようだし今回だけは大目に見ることにしよう。ただし条件がある。君は盗んだ物は3つだけだと言う。で もそれが真実かどうか分からない。もしかしたら他にも隠しているかも知れない」 「信じてください!盗んだのは本当に3つだけなんです!」 「最後まで話を聞いて」 「はい……」 「隠していないと言うのであれば、それを証明してもらわないとね」 「証明するって……どうやって……?」 「証明する方法は簡単だと思うけどね」 車野山は口元に隠微な笑みを浮かべながらつぶやいた。 ありさの顔色がみるみるうちに青白くなった。 「証明するってバッグの中身を全部見せればいいのですか?」 「それは当然だけど、それだけじゃ証明にはならないね」 「じゃあ服も全部脱げと言うことですか?」 「僕からどうしろなんて指示はしないよ。どうすればよいか決めるのは君だから」 「そんなぁ……」 プツンと会話が途切れふたりの間に沈黙が続いた。 バッグの中身を人前にさらけ出すことは私生活を覗かれるようで女性にとって快くはない。 いやそれだけならまだしも、衣服を全て脱ぎ去って見知らぬ男性に身体検査を受けることなど絶対に耐えられない。 でもここでそれを拒めば間違いなく警察へ通報されてしまうだろう。 ありさの瞼にキャンパスの風景が浮かんだ。 親しい友との語らい、人間科学の授業、ワンダーフォーゲルの野外活動、どれも失いたくはない。 ここまで頑張ってきたのに大学を辞めたくはない。 それに退学理由が分かれば今後の就職も難しくなるだろう。 長い沈黙を破ったのはありさだった。 まるで小鳥の羽根のように肩先を震わせながら小声で車野山に告げた。 「わ、分かりました……。おっしゃるとおりにします……」 BACK/NEXT |
 野々宮ありさ |
自作小説トップ
トップページ