気持ちいいこと ~乱夢白書~ |
|
乱夢子作 |
| 第1~4話 | 第5~8話 | 第9~12話 |
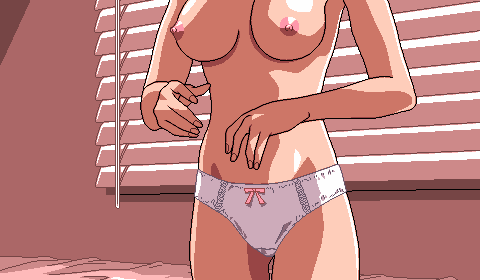 |
|
第5話
「あっ、いやっ、こんなの恥ずかしい、やだっやだっ!」 鏡に映っているわたしは、立ったまま脚を大きくがに股に拡げて、うしろから覆い被さってきている、その人のモノを受け入れていた。 シャワーの滴は、わたしの身体をつたってその人の身体へと、またその逆にも、激しく降り注いでいる。 「……恥ずかしくても、気持ちいいでしょ」 耳元で囁かれると、思わず小さくうなずいてしまう。 「あ、あああああ……」 小刻みに腰を揺すられると、身体中が痺れるように気持ちがよくなった。 そして前に回った手が、アソコの敏感な芽と乳首とを、いっしょにキュッと刺激する。 「だ、だめぇ」 裏返って、悲鳴みたいな声がでた。 だって、指もアレも、早く動いて止まらないから。 あまりに刺激が強くって、身をよじって逃げようとしても、ヒジや腕でしっかり押さえつけられていて、逃げられない。 「あっ、あああん、ん、んんっ……」 身体中に、電流みたいな強い快感が走り回って、それがちっとも出ていかない。 苦しくって、逃げたくって、でももっと欲しくって、わたしは自分でも知らないうちに、ぼろぼろ涙をこぼしていた。 「ああっ、あんっ、ああんっ、だめになっちゃうよぉ……」 泣きながらそういうと、耳元近くでクスクスと笑う声がする。 「じゃあ、もっとしてあげる」 アレがアソコを、もっと強く突き上げだした。 もう身体がいうことを聞かずに、こわばって、ぜんぜん動かなくなったみたい。 「あああああーーーっ!」 アソコの穴がビクビクビクンッと痺れると、自分でも驚くくらいの声が出て、目の前が一瞬まっ白になる。 「いっちゃったかな?」 身体がだるくて、力がぜんぜん入らない。 床に座りこんでしまいそうになると、その人は、わたしの身体をバスルームの冷たいタイルに押しつけて、無理矢理立たせた。 「ぼくもイクから、待っててね」 その人は、わたしのウエストを両腕で思い切りつかむと、めちゃくちゃに腰を振り立てた。 「ああっ、だめっ、壊れちゃうぅ」 アソコの中が強くこすれて、痛いわけじゃないけれど、これじゃあ刺激が強すぎる。 でももうわたしはパニックで、何にも考えることができない。 揺れて、揺すぶられて、噛んでた唇が痛くなったころ、耳元で大きなため息がして、その人はわたしを抱きしめてくれた。 「乾杯!」 バスルームでのえっちのあと、わたしたちは服を着て、部屋のソファーに座ってビールで乾杯した。 その人は、コップに並々とついだビールを、おいしそうに飲み干した。 わたしはあまり飲める方ではないので、ほんの一口だけだ。 「でも、きみはほんとに激しいコだね。こういうこと、けっこう続けてるの?」 「……うーん、今日が三回目なんですけど」 いやな話だな、と思った。 どうせわたしたちは、大人と子供だ。 こういう会話にどういうオチがつくのかは、なんとなくわかってしまう。 ムカついたけど、相手は『お客さん』だから、顔にださずにニコニコ笑った。 「お金、何に使うの?」 「家賃」 「……家賃って?」 「だから、家賃ですよ」 「ふーん。誰かといっしょに住んでるの」 「一人。親、死んだから。高校もそれでやめちゃったし」 「えっ、それってほんと?」 相手の人は、ちょっと不愉快そうだった。 きっと、わたしがウソをついているのだと思ってるのだ。 心底ムカつく。もう我慢しない。 「なによ。じゃあ、ブランド物のバックが欲しくてとかいえば、満足なわけ? だいたい理由なんて、あんたに関係ないでしょう。もう最低。帰るから、お金ちょうだい」 思い切りにらんで、立ち上がった。 「いや、ぼくが悪かった。正直いって、そういうヘビィな理由だと、罪悪感がわくからね。ちょっと待ってて」 その人はうろたえもせず、胸のポケットからサイフを取り出し、一万円札を四枚と名刺を一枚差し出した。 名刺には、デザイン事務所『コロニー』の代表取締役と書いてある。 「ぼくの名前は、谷口 登(たにぐち のぼる)。よかったら、また来週会ってくれる? できたら、その次の週も。料金は、今日と同じぐらいしか払えないけど」 「えっ、あ、それは、別にかまわないですけど……」 「じゃあ、決まり。ところで、きみの名前は?」 「湯原真由梨」 「いい名前だね。ぼくの会社、できあがったばかりなんだけど……こうやって何もかもが軌道に乗ったら、真由梨ちゃんみたいなかわいいコと付き合いたいって、ずっと前から思ってたんだ」 谷口さんは立ち上がって、わたしの手をとり、キスをした。 「きみの携帯も教えて」 さしだされたメモに、携帯番号を書いてわたした。 「ありがとう。じゃあ、ぼくから電話かけてもいいかな」 「はい」 もう一度、こんどは耳にキスされた。 はなれるときに、横顔をちらっと盗み見る。 どうしても、目にするそばから忘れてしまう。 どうしてだろう。 谷口さんの、不思議な顔。 「それと……真由梨ちゃんには、彼氏いる?」 「今は、いません」 「そうなの。できればさ、当分えっちは、ぼくとだけにしてくれない?」 「そうですね」 答えて、ぷっと吹き出してしまった。 谷口さんは、今は好きでも嫌いでもない。 これから、好きになっていくのかしら。 すこし変わった、でも趣味のいいスーツを着た谷口さんのあとから、わたしもいっしょに部屋を出る。 スーツから樟脳のにおいがしたので、ふと左手を見てみたら、やっぱりちゃんと、薬指には指輪をしていた。 「ウチの店、ロッカーないから。このポールハンガーにコートをかけて、バックは下の網棚に置いて」 「おサイフとかは?」 「レジの脇に小さな手提げ金庫があるから、そこにいれるの」 「あー、そうなんですか」 この、コンビニの先輩の松井っていう人は、ほんとにまったく無愛想だった。 茶の髪の毛がサラッとしてて、目も眉毛もビッとしていて悪くはないのに、何かこう、とっても話づらいのだ。 「よっ!」 そこへ、店長がやってきた。 「松井、ほんとに済まん。あがっていいぞ」 「はい」 松井さんは首をコキコキ鳴らしながら、タイムカードを押しにいく。 「いやあ、真由梨ちゃんに会いたいもんだから、松井に無理いって、深夜から今まで入ってもらっちゃった。申し訳ない。じゃ、客が来るといけないから、おれ、ちょっと店に出てるね」 店長はそれだけいうと、バックルームをあとにした。 「あのう」 「何?」 「松井さん、迷惑かけちゃってすみません」 「えっ、何それ。だって、湯原さんのせいじゃないでしょう」 「あ、ええまあ」 「じゃあ、あやまることない。それより制服着て、早く店に出た方がいい」 そういうと、松井さんは制服を脱いで、帰ってしまった。 それはたしかに、いう通りだけど。 ああわたし、どうしても松井さんって、苦手だなあ。 第6話 「んでさ、宅配便はね、一覧表が下にあるから。お客さんに送り状書いてもらってる間に、縦・横・高さをこれで計って金額決めるの。あと、特に重いのは料金が別だから、計るとき、必ずちょっと持ち上げてみてね」 「はーい」 このコンビニのアルバイトは、けっこう性に合ってたみたいで、わたしは毎日店に行くのが楽しみだった。 なんといっても、設計事務所の仕事よりぜんぜん楽で責任もないし、お客さんにニコニコするのも、考えてたより気分がいい。 「んじゃ、この表、元に戻して」 わたしは店長から、ビニールシートにはさまった料金表を受け取って、レジのところのいちばん下の引出に入れようと、身体をぐぐっと折り曲げる。 「あれぇ。真由梨ちゃんって、身体、異様に固くない?」 「ええっ、そんなことないですよぉ」 「ねえ、ちょっと前曲げやってごらん」 わたしはけっこう悔しくなって、足の爪先に指をつけようと、身体を思いっきり前に曲げてみた。 指は爪先に、かすりもしない。 「ほれみぃ、固い。おれはちがうぞ」 店長が前屈すると、手のひら全部が床にくっつく。 「くっ、悔しい~」 「わっはっは、ざまをみろっ。もうこれで、おれのことはオヤジ扱いさせないぞ……んでも真由梨ちゃん、おしりの形がかっこいいね。前屈すると、よくわかる」 店長の目は、丸眼鏡の奥で糸のように細くなり、垂れ下がる。 「やだあ、店長ったらセクハラオヤジ。いくら身体が柔らかくても、心はりっぱなオヤジじゃないですか」 「えーっ、男だったら誰だって……」 「若いコはね、思ってたっていいません」 「ちぇっ」 こんなふうに店長は楽しい人だし、気の合わないと思っていた松井さんも、とっつきにくいけど、細かい所まで仕事を教えてくれるいい人だった。 でも……というか、やはりというか。 そうそう何もかも、いいことばかりないみたい。 もうひとつの『アルバイト』の方が、実はけっこうしんどくなってきたのだ。 「あっ……ああんっ、真由梨、気持ちいい……」 クチュッ、クチュッと小さな音が、シーツの隙間から聞こえて来る。 谷口さんの右の手が、わたしのアソコをぴったり塞いで、やさしく揉みこむ。 あの、デザイン事務所の社長をしている谷口さんとは、今夜で会うのが四回目になる。 谷口さんはやさしいし、えっちの前には、すごい料理もおごってくれる。 いや、そんなことより「大人の女の扱い」をしてくるのが、とってもうれしい。 エレーベーターやタクシーとかに乗るときは、必ずレディファーストだし… …だからといって、いつもデレデレ甘やかすのともまた違う。 例えばわたしが「アルバイト先で、ちょっと合わない人がいてぇ……」なんて言い出したなら、「そんな話は聞きたくない」ってとたんに顔に現われる。 とても微妙なバランスを、気をつけながら、とってくれるのだ。 わたしもそれに答えたいって、会うたびいつも思ってる。 でも、なのに。 「真由梨ちゃん、自然にしてて、いいんだよ」 ささやく声が、甘くやさしい。 そう。谷口さんは、やさしい人。 抱かれていると、とろんと眠くなるくらい。 「もう、来て……」 わたしも耳に、ささやきかける。 もう、いいの。別に感じなくったって。 谷口さんに入れてもらうと、とても幸せになるんだもん。 「……それが、ちょっとダメなんだ」 「えっ?」 谷口さんが、身体を離した。 お腹や胸に、エアコンの乾いた風が吹きぬける。 「ごめんね。もう、終わりにしよう。ちょっと服着てくれないかな」 谷口さんは、寂しそうに笑っている。 わたしは黙ってうなずいて、いうとおりに服を着た。 「正直にいう。最近、仕事が忙しすぎて、いつもイライラしてるんだ。きみと会っても、集中できない。それにその……」 谷口さんは、定期入れから写真を出した。 三つぐらいのかわいい女の子と、きれいな……たぶん奥さんだろう人が、写ってる。 「きみと会うとさ、どうしても、子供のことを考える。そうすると、何でこんなことしてるんだろうって、思えてくる。きみだって、まだ子供じゃないか。自分がさ、最低のヤツに思えてね……」 それは不思議な、ながめだった。 男の人が、こんな大人の男の人が泣くところ、わたしは見るのがはじめてだった。 泣いている、谷口さんが、ぼやけてく。 ああ、わたしも泣いてるんだと、人ごとのように考えた。 「……谷口さんの、そういうところ、大好きです」 わたしは谷口さんにすりよって、ひざに置かれた手をにぎり、しばらく泣いた。 ふたりで、ただ黙って泣いた。 それでとてもおかしなことに、ひどく幸せな気分になれたのだ。 「それでその、これはとっても、言いにくいんだけど……」 谷口さんは、テーブルの上のティッシュをとって、わたしの涙もぬぐっていった。 「あのさ、その、大学時代の友人で……きみに興味があるヤツがいて……」 「はっ?」 「人に勝手にしゃっべたことは、謝るよ。ほんとにごめん。たださ、こういう……援助交際っていうやつは おそらくきみも、止められないでしょ。そしたらさ、いつヤクザにひっかかるとも限らないし。だから……よかったら、そいつのことを、紹介させてくれないかな……なんて思ってさ」 わたしはとっても驚いて、そしてそのあと安心した。 たしかにわたしは、この先しばらく、こういうことはやめられない。 谷口さんの友達ならば、きっといい人だろうと思うし。 「……そうですね。それならわたしも、助かります」 「ごめんね、真由梨ちゃん」 谷口さんは、おでこにチュッとキスしてくれた。 そのときはじめて奥さんのことが、とってもとっても妬けてきた。 一週間後、いわれた通りに、ある中華料理店にやってきた。 中華料理のお店なのに、そこはちっともケバくなくって、とても高級そうだった。 一人で入るのに、勇気がいった。 「あの、谷口さんは、どこでしょう?」 「こちらになります」 チャイナドレスをきれいに着こなした女の人に、店の奥まで案内される。 そこは、小さな部屋になってるらしい。 ドアの向こうから、声が聞こえる。 「……いやあ、店に入った女の子でサ、やっぱ似たような境遇のコが、いるのよこれ。かわいいコでさ、仕事もまじめでよく気がつくし……やせてるのにね、ムネとかシリとかりっぱでさ、そういうコだと、おれうれしいな……」 いやな予感。 最悪の答えが、頭の中を駆け抜ける。 いや、まさか。 でもやっぱり……なんといっても、声が似ている。 「お連れ様が、つきました」 「アーーーーーッ!」 丸眼鏡で、髪がふわふわパーマの人が、椅子から立ち上がって叫んでいる。 そう。事態は最悪だった。 「……店長」 ああ、何もかもおしまいだ。 わたしは二つのアルバイト先を、今日一日で、失くしちゃうのだ。 第7話 谷口さんと店長は、美大時代の悪友らしい。 三人の前にある中華料理店の丸い卓の上には、海老のチリソース炒めやホタテの煮物や牛肉の煮込みが、とろりと光ってきれいだった。 店長の顔を見るなり、いそいで逃げ出そうとしたのだが、どういうわけだか二人とも、ダッシュで走って来て、わたしのことを引き止めたのだ。 店長はひっきりなしに老酒を開けていて、もうすっかりグデングデン。 「結婚するのもさぁ、会社を興すのもさぁ、おれが両方先にやって、両方先に失敗したわけでさあ……」 まるで自分の話じゃないみたいに、店長は昔話をする。 「おい、先にっていうけどね、おれはおまえみたいに失敗しないぞ、両方ともな」 谷口さんもけっこう飲んで、もうだいぶ顔が赤かった。 「そうね、そうだね。でも、若い彼女はおまえが先で、やっぱ失敗しただろう? おれは今度は、うまくやるから」 あれ、店長、わたしと付き合うつもりなの? そんな二人の会話を聞きながら、食はちっとも進まずに……なんてわけはなくて、エビもホタテも牛肉も、みっともないほどガツガツしながら食べている。 「じゃあ、おれは先に帰るよ。あとの話は、二人で決めて」 杏仁豆腐が出てきたころ、谷口さんがふいにに立ち上がって、伝票をとった。 「おい、おれが払うって」 すかさず店長が、不機嫌そうな声でいう。 「いいの。真由梨ちゃんに、最後のごちそうしたいから」 谷口さんが伝票をヒラヒラさせながらそういったとたん、わたしはひどく悲しく、そして心細くなってしまった。 「いろいろと……どうもありがとうございました」 「いやいや、ぼくの方こそ、感謝してるよ」 谷口さんは軽く、ほんの少しだけ寂しげに笑って、早足で部屋を出ていった。 とたんに部屋が、寒々しくなる。 でも視線を感じて、つっと振り向くと……店長が、恐い顔をして座っていた。 いや、無表情なだけなのだが、それがほんとに恐いのだ。 特に、丸い眼鏡の下の目のあたり。 店長って、こんな恐い顔できたんだ。 「ホテル行こう」 「えっ?」 「おれじゃ、イヤなの?」 「あの、いえ、そんな……」 「じゃあ、行こう」 店長が、すばやく立ってツカツカこっちへ歩いてくる。 わたしは、いきなり抱きしめられた。 「おれ、前から、あなたとやってみたかった」 髪の中に手を入れられ、頭をつかまれ、キスされる。 長い舌で、わたしの舌はからめとられて、だんだん息ができなくなる。 店長のことが、なおさら恐くなってきた。 そして恐いと感じたとたん、まるでおもらししたみたいに、アソコから液がジュンッと垂れてくるのがわかった。 一度くちびるが離されて、もう一回キスされる。 店長の手が、蠍みたいに這いだして、スカートのすそに入りこむ。 パンツの上から、アソコを強くつかまれた。 「すごいなこれ。もう、準備OKなわけ?」 そんなことをいわれたけれど、ひどいめまいがして、もう、何も答えることができなかった。 タクシーに乗り、シティホテルに入ってからも、店長はほとんど口をきかなかった。 昇っていくエレベーターの中で、わたしは窒息しそうな気分。 部屋にたどり着くまでも、廊下をとっても長く感じた。 「風呂、いっしょに入ろう」 部屋に入ったとたん、店長はそういって上着やズボンを脱ぎはじめた。 「あ……はい」 わたしは答えて、店長がシャツとパンツだけになるのを待ってから、おもむろに服を脱ぎはじめる。 万一先に脱ぎ終えちゃったら、そりゃああまりに恥ずかしすぎる。 「おいで」 店長は裸になっても、ぜんぜん恥ずかしくなさそうだった。 アレなんか、もうぶらぶらしないで、まっすぐこっちを向いている。 胸とアソコをおさえて立ってたわたしの手首をつかむと、引っ立てるようにシャワールームへ大股に歩いていく。 コックをひねり、シャワーの温度を確かめると、それをいきなりこっちへ浴びせかけてきた。 「彼氏、いるの?」 「今は、いません……」 シャワーの水圧が強い。こんなふうに質問されると、何だか拷問されてるみたい。 「じゃあ……お金、上乗せするからさ、ひとつお願いがあるんだけれど」 「なんですか?」 「それはね……」 店長はいいかけるなり、シャワーを放って、わたしに飛びかかってくる。 「ひっ」 抱きとめられ、腕の中でくるりと回され、小さい子供におしっこさせるみたいに、太ももを持たれて抱き上げられた。 店長はわたしを抱きかかえながら、二三歩バスルームを歩く。 「やっ、いやあっ」 正面にある細めの長い鏡には、両脚を拡げ、パックリ丸見えにさせられている、わたしの姿が映っていた。 「ここをね、全部剃っちゃいたいの。真由梨ちゃんがね、気紛れでも、他の男とやらないように」 「いやですっ!」 「なんで」 「だって、そんなの恥ずかしすぎるっ」 「すぐに終わるよ。でもさ、女の子って、顔とアソコが似るらしいけど、真由梨ちゃんはどう思う?」 店長はわたしを鏡に近づいて、太ももを抱えた手を広げ、皮膚を攣らせて、なおさらアソコが広がるようにしむけている。 わたしはなるべく見ないようにしてたけど、身をよじるたび、どうしても目に入ってしまう。 ウワサには聞いていたけど、何ともいえずにグロテスクだ。 「それともあれか、ここにやっぱり他のヤツのを入れたいわけか」 「……そんな、ちがう」 「なあ、いいだろう? おれ、一度でいいからやってみたい」 甘えたようにいうけれど、店長は、こんなに長くわたしを抱えて、ぜんぜん平気でいるらしい。 圧倒的な力というのは、やっぱりすごく、恐いものだ。 出しっぱなしのシャワーの音が、やけに耳についてくる。 わたしはだんだん……何ていうのか、恐がったり悩んだりするのに疲れてしまって、とうとうコクリとうなずいてしまった。 「よし、決まり! 真由梨ちゃん、ありがとうっ」 店長はそっと、わたしを降ろす。 「ちょっと、がまんね」 「あんっ」 わたしはぴったり、壁に背中をくっつけられて、冷たさに小さく悲鳴をあげる。 「脚はMの字っていうのは、お約束だよなあ……」 脚は、ひどい形に拡げられた。 「はい、じっとしててね」 ボディソープを泡立てられて、アソコのモシャモシャの上に、円を描くように塗られていく。 「……いやっ」 カミソリは、冷たくなんかなかったけれど、それでも刃物の感触は、わたしをとっても緊張させた。 音はしない。けどゾリゾリという感触が、柔らかな肉の丘を伝うのが、はっきりわかる。 「動かないでね。ここは、ちょっとむずかしい」 カミソリが、おしりの穴の方へ向かって進んでいく。 入り組んだ場所に、カミソリが当たる。 ソコに顔を近づけられてて、わたしは思いっきり恥ずかしかった。 「ほら、できた」 出しっぱなしのシャワーでアソコをきれいに流すと、店長はわたしをひょいと抱き上げて、もう一回鏡の前で、さっきと同じかっこうにした。 「もういいですっ」 それでもわたしは、ちらっとだけ見てしまった。 アソコの毛の剃られたわたしは、アンバランスに若返り、一部分だけ子供みたいで、ちょっと痛々しいほどだ。 やがてわたしは降ろされて、店長に抱きしめられた。 「おれここに、自分の名前を書いちゃおうかな?」 店長は、顎をつかんでキスしようとした。 キスする前に笑顔になった店長を見て「あっこの人、二人っきりになってから、はじめて笑った」とわたしは思った。 第8話 店長はわたしのことを、バスタオルで……耳の裏側から乳房の下側、アソコから足の指の間まで……よく拭いてから、ひょいと(いや実際は、けっこう重そうだったかも)抱きかかえて、ベッドの上に放り出した。 「きゃあっ、乱暴!」 「いっただっきまーす」 ダイビングするように、ベッドに飛びこんでくる。 激しくきしむ、ベッド。 両頬を挟みこまれての、強引なキス。 剃り上げられたアソコの方に、手がじわじわと伸びてきて、ぷくぷくした肉の合わせ目に、指がつるりと入っていく。 「じゃあ、もうだいじょうぶみたいだから、最初から入れちゃおう」 店長は身体をおこすと、太ももをこじ開けるように開かせて、アレをアソコにあてがって、いきなりぐいっと進入してくる。 「あっ!」 脳天までズンッと響くような快感が、身体の奥まで突き刺さる。 店長のアレは、ほんの二十センチほども、身体の中に入っていないはずなのに、心臓のすぐ下まで、アレが入ってるように思える。 店長が、アソコの敏感な芽をいじくりまわす。 「あっあっ、ソコはダメっ」 「んん? 何よ、ソコじゃあ判らないよ。何がダメなの?」 「あああああ、ソコ、なんていうのか知らない……」 「マジで?」 「ほんと……」 店長は、プッと吹き出す。 「あのね。ここはね、クリトリスっていうんだよ」 「あ、ああんっ、そんなにいじっちゃ……」 「そう。じゃあ、いってこらん」 「えっ、店長、ああ……クリ……トリス」 「よくいえました。それとおれのことは名前で呼んで」 「細見さん?」 「俊哉でいい」 「呼び捨てって、なんか……あんっ」 店長が、クリトリスをキュッとつまんだ。 奥まで入れられてるところが、じんじんと痺れるようによくなってくる。 背中を丸めた店長が(どうしても、俊哉っていうの、なじめない)、チュクッと音をさせて、乳首の先に吸いついた。 ああ、もうアソコの奥が、ジュクジュクって熱くなって、腰が勝手にモソモソしちゃう。 「あっ、あっ、あああんっ、ああ……」 「気持ちよさそうな顔して、コイツ」 店長が、人差し指と中指二本で、ほっぺたをなでるようにたたく。 そして、もう一度胸を吸われた。 「んっ、んっ、ね、もうしてっ、してよぉ……」 自分でも、何をいってるのか、もうわからない。 アソコから、熱い液がとろりと勝手に降りてくる。 「しょうがないな……」 店長は、わたしの背中に両腕を回して、ギュッとキツく抱きしめると、むちゃくちゃに早く腰を使った。 「あうっ、あ、ああっ……」 息が止まる。こういうのって、どんな絶叫マシーンより、絶対に興奮するとわたしは思う。 アソコの奥が、キーンと熱い。 そこにはきっと、グジュグジュのアメーバみたいな生き物が、たぶんピクピク痙攣してて、そいつがキュッと、縮こまって固まるときに、わたしもイクんだと思う。 ああでも、男の人に、こうして抱きしめられるのって、いい。 このままシュワッと、消えてしまいたい。 店長は、眼鏡をとると、顔がすこし地味になる。 そういうところも、けっこう悪くないと……と思いかけたとき。 身体がグジャリとよじれるような感じがして、そのままトロトロ、アソコから熱い液を出しながら、ほんとにふいに、イッてしまった。 終わったあとで店長は、お金をくれて、タクシーを呼び、わたしを一人で家に帰した。 「送っていって、家とか、はっきりここってわかったら、おれ、きっと入り浸っちゃう」 ということだそうだ。 A.M 1:00。 中華料理屋にいったのが、六時半ごろだったから、もう六時間以上たっている。 夜のタクシーの窓ガラスは、何でも映す。 不思議とこれっぽっちも、うしろめたくなんてなかった。 その前の人までは、何だかすこし、気の引けるとこがあったんだけど、どうしてだろう、店長が相手だと、ぜんぜん悪いという気がしない。 でもそれは相手のせいじゃ、ぜんぜんなくって、ただ単にわたしが馴れただけかもしれない。 「おはようございます」 「おはよう」 大学生バイトの松井さんは、相変わらず愛想のない挨拶だ。 でもそんな、いつもと変わらないぶっきらぼうさが、ちょっとわたしを安心させる。 やってきた『焼き立てパン』の並べ方を、ていねいに教えてくれるところなんか、やっぱりうれしい。 店長のこと、ぜんぜん悪いという気はしないけど、この人といっしょにいると、ちょっと心が痛くなる。 「あのさ、店長のことだけど……」 「はっ?」 あぶないあぶない。 耳まで赤くなりそうになって、あわてて「だいじょぶ、だいじょぶ」と、平静を装うのには、苦労した。 「……なんか、いいにくいけど、あの人ね、たまにお店の女の子に、いいよるみたいで……」 「はあ……」 「いや、それは別にどうこういう気はないし、店長は基本的にいい人だしね。でも……それで辞めちゃうコも、いるんだ」 「ええ……」 「だからその、気をつけてね。あの、真由梨ちゃんには、辞めてほしくないからさ」 「はい……」 「……うん。また他のコに一から教えるの、たいへんだしね」 そういった松井さんの方が、耳まで赤くなっている。 なんだかね、素直にうれしい。 ちょっと最近、悪いと思わないまでも、普通じゃないとは、思うようになってたから。 松井さんの普通さが、今のわたしには、とてもまぶしく感じられる。 「あ、おはよう」 そこへ店長がやってきた。 「松井、あがって。おつかれさん」 ちょっとバツが悪いのか、松井さんはひょこっと頭を下げただけで、そそくさとバックルームに消えてしまった。 「……なんだよ。松井、真由梨ちゃんに迫ってなかった? ちょっと様子がおかしいぜ、あいつ」 うわあ、こわい。 店長って、けっこうするどい。 「別に、何でもないですよ」 「なら、いいけど。でもあいつ、真由梨のココのこと知ったら、どんな顔、するんだろう」 そういって店長は、カウンターで外からは隠れている、わたしのアソコをジトッと触った。 「……やめてください」 キッとにらんだつもりなのに、店長はニタニタしている。 「いらっしゃいませ」 同じ年くらいの女の子。 今日は高校、休みなのかな。 それとも、さぼってるのかしら。 あ、ちょっとヘン。まっすぐこっちへやってくる。 「あのぉ、バイト募集の貼り紙、見たんですけど」 細いコだなあ。 それに顔が小さくて、顔立ちがはっきりしてる、今時の女の子。 「んじゃあ、こっちに来てくれる?」 店長は、そのコのことを、バックルームにつれていった。 いいなあ。 ああいうコと、いっしょに仕事がしたいなあ。 だってわたし、同じ年のコがそばにいること、最近ぜんぜんなかったんだもん。 つづく |
投稿官能小説(1)
トップページ