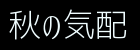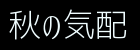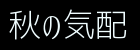
 |
夏の終わり、朝夕めっきり涼しくなってきた。
私は、決まり切った仕事の後、家に帰ってくると彼からの電話をずっと待っていた。
メールじゃだめ。声が聴きたいから。
テレビのドラマが終わり、いつのまにか深夜になっていた。
涼しくなったためか、窓の外では秋の虫の声が響いている。
もう12時。
とうとう私は電話を諦めた。
カーテンをきっちり閉めなおした。
電気を消すと薄明かりだけが部屋を支配した。
(もう寝ようかしら)
最後の電話から1週間、喧嘩のようにして別れてしまった。
後悔していた。
自分から謝ればまだ元に戻れると思うけど、気が進まない。
失って初めて分かる彼の温もり。
週末はいつだって私の部屋か、彼の部屋にいた。
薄暗い部屋の中で、私は彼の温もりの優しさを思い出す。
私は寝間着代わりのTシャツをすっと脱いだ。
薄手のカーテン越しの街のネオンのチカチカを見ながら、背中から彼が抱いてくれる光景を思い出していた。
身体が熱くなってくる。
ぴったりだ、と彼が言ってくれた胸の膨らみに手をやった。
自分の手では溢れる。
彼の大きな両手だとぴったりに胸は隠れた。
肌が合う、そんな言葉を思い出した。
胸に触れる、その彼の手のひらの温もりを身体が憶えている。
胸の辺りが触れられたようにふ~っと心地よく熱くなっていく。
あっ、この感じ。
(あたし、彼に染まってる)
私は分かっていた。
肌が鋭敏に彼を求めている。
背の高い彼が、自分を後ろから強く抱擁しながら、首筋へキスをしてくれる。
あの身体が融けていくような時間を思い出していた。
彼は何も言わず黙ったまま私を抱いた。
まるで止まったように動かない。
包み込まれたまま、二人の時間が止まってしまったように過ぎていく。
呼吸が1つになり、心臓の音が1つになり、心が1つに融けていく。
至福の時間。愛されている喜びが身体中に満ち溢れていく。
もうこのままずっといたい……そう思い続けてしまう。
私は身体中で彼を思いだし始めていた。
まるで抱かれているように。
「俺は悪い虫だから」
彼はそんな風に言い訳をして肩の窪みへの痛いくらいのキス。
痣のようなキスマークも、もう消えてしまったけれど、感覚は憶えている。
彼の熱いものは手が憶えている。
後ろから抱かれながら、手を伸ばすと、もう熱くなっている。
手触りがよくてぎゅっと握ってしまう。
親指で頭をいじると彼がふっと腰を引く。
「感じちゃうよ」
彼が耳元で言う。
素直で、少年のような彼の声が素敵だった。
すぐに彼の右手が私の身体を探ってくる。
立っていられないくらいの電流が身体中に流れ、彼の熱いものが欲しくなる。
私は着ている物を脱ぐと、ベットに横たわった。
彼が実際はいないという空しさはあったけれど、心の中にも身体中にも彼が満ち溢れていた。
彼の熱い物を受け入れる時のように、大きく足を開くと自らの指をそこに滑らせた。
彼が入っているっていう感じにはほど遠いけど、そうでもしなければ収まりそうにない。
窓の外では相変らず秋を告げる虫の音が響いている。
どこか物悲しそうに……。
完

★乱夢子さん投稿作品一覧★