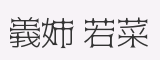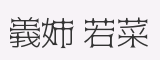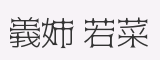

|
階下からずっと聞こえてくる宴会の騒がしさに、勉強中の中西誠は頭を抱えた。
「駄目だ、こりゃ。何も頭に入らない」
実は今日、我が家では近々、結婚する従兄が奥さんを連れて挨拶に来た為、親戚中が集まってお祝いをしている。
お調子者の父が急遽、取り決めたのだが、来年、大学受験を控えた誠としては、本当に迷惑極まりない話だった。何せ、近隣の親類縁者が集まれば酒も出るし、そう簡単にお開きとはいかないはずで、すでに追い込みの時期だが、今日は勉強を諦めるしかなさそうである。
とは言えやる事も無いので、階下に足を運んでみると、結婚する従兄と奥さん、父母、それに親戚と兄夫婦がそこにいた。兄、隆は誠の顔を見ると、隣に座っている妻、若菜に向かって、
「おい、あいつにスイカでも切ってやれ」
と、言った。
「はい」
若菜が立ち上がり、誠を台所へ手招いた。
「ごめんね、誠。うるさいでしょ?」
若菜は冷蔵庫からスイカを取り出すと、それを四つに切った。
「いいんだ。それよりなんだよ、兄貴のやつ。姉さんを顎で使って」
「お父様たちがいるから、良い格好をしたいのよ。普段はああじゃないわ」
ふふ、と笑うと、優しげで美しい。誠はこの義姉の笑顔が好きだった。
「ねえ、誠。あなたの部屋に行っても良い?」
「いいけど、テレビも何も無いよ」
「いいのよ、そんなの」
若菜は誠の肩を掴み、ふざけて体を押し付けてきた。背にふくよかな二つの母性が感じ取られ、誠は赤面する。
(柔らかい)
衣服越しでもそう思う事が出来、誠の下半身には激しい変化が起こっていた。
二人は誠の自室にこもると、向かい合って話をする事にした。もっとも兄嫁と何を話せばいいのか誠が戸惑っていると、
「誠、ちょっとお願いがあるんだけど」
若菜は上目遣いで、そう言うのである。
「何を?」
「言いにくいんだけど」
一呼吸置いてから、若菜は声を顰めて呟いた。
「私と・・・して欲しいのよ」
・・・の部分は、更に声を落としたのでよく聞き取れなかったが、誠の脳には淫猥な四文字が刻まれたような気がする。
よもやと思い、もう一度、聞き返すと、
「・・・セックスしようって言ってるのよ」
若菜は顔を赤くして、囁いたのである。
「何言ってるの、姉さん・・・」
「真面目な話なのよ」
きゅっと眉をしかめ、若菜は言うのである。
「ねえ、誠。私とあなたのお兄さん、結婚して何年経つか覚えてる?」
「三年でしょ」
「そう。それで最初の一年間、獣のようにエッチしたんだけど、子供が出来ないのよね」
「うん」
「二年目は間を置いて、週一のペースで・・・結果は見ての通り」
若菜は手を大きく広げて、駄目でしたという感じの動きを取った。
「私も焦っちゃって・・・今でも週一のペースは守られてるけど、それらしい兆候は皆無なの。そこで、私、ひらめいたのよ。活きのいい誠の子種だったら、すぐに妊娠するんじゃないかって」
「そうかなあ・・・」
「血液型も同じだし、何より兄弟だからどちらの種で妊娠しても、私としては何の問題も無いのよね」
「おかしいよ、その考え方」
誠はこの突拍子も無い考えに難色を示した。義姉の事は好きだが、それとこれとは話が違う。いくら子供が出来ないからとはいえ、まさか兄に代わって若菜を妊娠させる訳にもいかず、どうしたものかと思案に暮れるのだった。
「誠は、私の事、嫌い?」
「まさか!」
「嘘、本当は嫌いなんでしょう・・・」
「そんな事は絶対に無いよ」
「じゃあ、それを証明して見せて」
若菜はとろんと目を潤ませ、女の武器を使ってきた。自分が無茶を言っているのに、相手に罪悪感を持たせる戦法である。分かりやすく言うと泣き落とし。
「灯かり落とすわよ。そうしたら、すぐに服を脱いでね」
「ちょっと、姉さん」
若菜の手が蛍光灯のスイッチに伸びたと思うや、部屋がふっと暗くなった。カーテンは開いているので月明かりこそ差し込むが、目が慣れるまでは心許ない。
誠は手さぐりで若菜を見つけようとするのだが──
「あん」
むにゅりと柔らかな物を触ると、若菜の声がした。どうも乳房に触れたらしい。
「ご、ごめん、姉さん」
「何を謝ってるのよ。もっと、やらないと」
若菜が誠の手を取り、胸へいざなう。すでに彼女は上着を脱ぎ、ショーツ一枚になっていた。
「私、胸が凄く感じるの。お願い、触って」
若菜は背を向け、自分の髪を両手ですくってかきあげた。背後からやってくれと言うのである。ここまで来ると誠も迷う事は無く、両手を伸ばし、義姉の乳房を揉み、乳首を指で啄ばんでみる。
「あっ・・・」
硬くも無く柔らかくも無い、不思議な塊を指先で扱き、いやいやをする若菜のうなじに口づけをする。誠の股間は痛いほど充血し、早く下着の戒めから逃れたいと叫んでいた。
「誠、私に何か命令してくれない?」
「どうして?」
「その方が燃えるのよ」
若菜は自ら被虐者になりたいと思う性癖がある事を告白した。誠は面食らいつつも、
「じゃあ、ベッドに四つん這いになって」
と、義姉と寝床に追いやるのである。
「ねえ、誠。もっと命令して」
「うーん、じゃあ・・・今から俺の質問に答えて。初体験はいつ?」
「十六の時」
「誰と?」
「家庭教師をやってくれてた大学生」
「兄貴と結婚するまでに、何人と付き合った?」
「・・・九人」
「多くない?」
「普通よ」
「兄貴は知ってるの?」
「まさか」
若菜は笑って答えた。
「あの人は、私を貞淑な方だと思ってるはず」
「じゃあ、これは兄貴も知らない俺と姉さんとの秘密って訳だ」
「素敵ね」
若菜はこの時、誠に下着を脱がされる瞬間を、今か今かと待ち望んでいる。そして逞しい男性で、奥の奥まで肉穴を貫き、活きの良い子種を放って欲しかった。
「誠──ううん、誠様。そろそろ、私にお情けをくださいませ。あと、私の事は若菜って呼び捨てにして」
「いいだろう」
誠は這っている若菜の尻から、ショーツを脱がしにかかった。尻の割れ目に鼻を近づけると、肉穴と排泄孔から漂う微かな臭気に股間が熱くなる。
「俺が欲しいのか」
「はい」
「ねだってみろ」
誠はズボンを脱ぎながら、若菜に命じた。
「これを私にくださいませ。そして、中で思いっきり、射精してください」
「もっと下品に」
「私を・・・若菜をあなたの子種で孕ませて。私、誠様の子供が産みたいわ」
「いいだろう。じゃあ、入れて欲しい場所を指で開くんだ」
最初は言葉遊び程度のつもりだったが、いつしか誠も女を征服したがる男になりきっていた。
逆に若菜は年上である事を忘れ、支配される喜びに打ち震えている。
「これでよろしいでしょうか」
指で逆V字に肉穴が開かれた。誠はそこに怒張した己自身をあてがうと、一気に腰を前に出す。
「あううッ!」
「どうだ、俺のは」
「素晴らしいです・・・ううッ・・・」
やや厚めの花弁を割き、誠は見事、侵入を果たした。肉の洞穴はしとどに濡れており、しかも全体が温みを帯びて柔らかく締め付けてくる。誠は前かがみになり、若菜をぐっと抱きしめた。うなじに口づけを嵐のように浴びせ、乳房を揉んだ。相手が義姉という事も忘れ、ただ女の肉を喰らおうとする、情欲そのものであった。
見下ろせば若菜は折れそうなほど細い体である。目が暗さに慣れ、月明かりでも女体の線が分かると、誠はその細い腰を掴み、これでもかと男を送り込んだ。若菜は階下の事を慮り、声を殺し身悶えるのだが、その様がいじらしくて誠は昂ぶった。
更に子種は全て彼女の中に放出し、ただの一滴も残さぬ事を心の中で誓ったのである。
十ヵ月後、受験を終えた誠の所へ、若菜が現れた。すっかり大きくなったお腹を抱え、顔は母親になりつつある。
「もう、産まれそうじゃないの?」
「ぼちぼちね」
誠は若菜の腹をさすり、近く産まれてくる我が子を愛で、また出産という大役を果たす義姉の事を労った。
「兄貴はどう?何か変わった?」
「あの人、毎日、早く帰ってくるようになったわ。産まれるのが待ち遠しいって」
「父さんと母さんも喜んでるよ。ようやく孫の顔が見られるって」
「いい事づくめじゃないの。やっぱり、私の考えは正しかったんだわ」
お腹の子の父親が誠という事は、無論、自分達以外に知る者は無く、また知られてはならない。
それさえ守秘されれば、すべてがうまくいく。誠と若菜は顔を見合わせて笑った。
「これで、俺はお役御免かな」
「何言ってるの、一人じゃ駄目よ。私、三人は欲しいの」
「欲張りだな」
「そうよ。女って欲張りなんだから・・・あっ」
「どうした?」
「今、お腹を蹴ったわ」
若菜はそう言うと、慈母の笑顔で大きなお腹をさすったのであった。
完