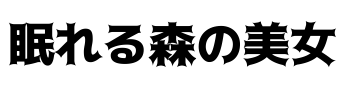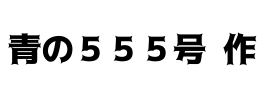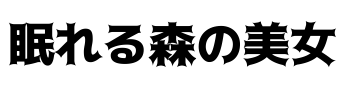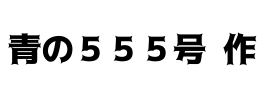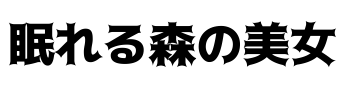
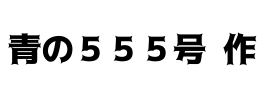 |
第4話
(さて、十年振りの御開帳だ)
王子は脱がせたパンティーを無造作に寝台の下に放り投げると、いそいそとオーロラ姫の両下肢の間に陣取った。
金糸で編んだかのようなオーロラ姫の叢が木漏れ日を浴びてキラキラと輝いている。10年以上もパンティーに押さえつけられていたとは俄かには信じがたいほどの柔らかな手触りに王子はうっとりとせざるを得なかった。まるで毛足の長い高価な絨毯を撫でているかのような手触りだった。縮れも少なく、まさに繊毛と呼ぶに相応しい陰毛は一本一本は透き通るようなプラチナブロンドなのだが、それが折り重なるにつれて徐々に重厚感のある黄金のような輝きを放っているのだ。そしてその金色のグラデーションの最も濃い部分、叢の中央部に走る黄金の筋こそがオーロラ姫の生殖溝と思しき部分なのだ。
王子は絹草のような草叢を丁寧に左右に掻き分けた。すると黄金のジャングルの奥に見えたのは抜けるように白いヴィーナスの丘だった。まるでナイフで筋を入れたかのようなシンプルなスリットは幼女のものと見紛うばかりの可憐さだ。ローズピンクに色付く切れ込みのあわいにうっすらと汗を浮かばせているのは王子の愛撫の所為だ。王子は高価な宝物を穢したかような背徳感に背筋を奮わせた。
鶏冠のようなラヴィアのはみ出しは微塵も認められない。唯一、スリットの上端に鎮座するフードを被った雌芯だけがほんの少しだけ顔を覗かせている。いっぽう、クレヴァスの下端にはオーロラ姫が心ならずも分泌したラブジュースが雫となって零れ落ちんとする所であった。
王子はオーロラ姫の秘められた部分をもっと仔細に観察するために彼女の両の膝頭に手を掛けてグイと長い脚を左右に押し拡げた。おそらく彼女がこれまでの生涯で、どんな場所でも取ったことがないと断言出来るほどのあられもない大開脚の姿勢だ。
オーロラ姫の秘められた部分が余す所無く王子の目に飛び込んできた。ここまでの姿勢を強いられては如何に無垢なスリットといえども、そのとじ目を綻ばせてしまわざるを得なかった。
オーロラの姿勢が変わった所為か、クレヴァスの下端からラブジュースの雫が今まさに零れ落ちる所だった。
王子が下着越しに看破した通り、オーロラのヴァギナは明らかな下付きだった。それ故にクレバスの下端とアナルが極端に近い。その僅かな距離をラブジュースの雫が煌めきながらゆっくりと下に転がり落ちてゆく。
オーロラのアヌスは端正な佇まいで、そこが排泄のための器官だという事を見るものに忘れさせるほどに可憐で精緻な造りだった。深い菫色をギュッと絞り込んだ小ぢんまりとした肛門には細かな皺が放射線状に刻まれており、まさに秘境の奥に咲く秘密の花に例えるのが相応しいものだった。中心の孔はピッタリと閉じられてはいるものの、オーロラの呼吸に合わせて窄まったり綻んだりと規則正しく蠢いている。
長い時間をかけて短い旅を終えた雫がようやく目的地のアヌスに達しようかという寸前、その歩みが鈍くなった。排泄孔の周囲がぷっくりと盛り上がっている所為で足止めを食らったのだ。雫が歩みを止めている間にも上流のクレヴァスからはジワジワとラブジュースが染み出してくる。
鮮烈なサーモンピンクが爆ぜた肉裂から顔を覗かせた。艶やかに輝く媚肉の色付きは、まだオーロラが男を識らぬ躯である事の証にも見えた。
王子はオーロラのもっと深い所をその目に焼き付けようと、彼女の股間に顔を寄せて柔らかな陰阜に指を押し当てた。ふわりと指先を包み込むかのような手触りは宮廷のベッドを思わせた。
(……開くぞ……)
王子は心の中でそう呟くと指先に力を込めた。
クチュッ……
湿った音と共に神秘の扉が開かれた。オーロラ姫の秘所の一端が今、外の世界に曝け出された。
ゴクッ……
ひりつく喉が上下して唾液を嚥下した。女のその部分など飽きるほどに見てきた筈の王子が我を忘れた。それほどにオーロラのヴァギナは美しかった。世界中に存在するありとあらゆるピンク色がオーロラの股の間に集約されているかのようだった。複雑精緻かつ微細な肉襞が幾重にも折り畳まれている様はまるで薔薇のようではないか。
王子は目を閉じて世界一高貴な花の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。日向の干し草のような匂いは黄金色の陰毛から立ち上るものだろうか。浜辺の風に運ばれてくるかのような磯の香がほのかに嗅覚を刺激する。どれ程神々しくても、やはりオーロラも人の子なのだと王子は安心した。その美しすぎる肢体に半ば気圧されかけていた彼の嗜虐心が再び頭をもたげ始めた。高貴な姫君だろうと所詮は女。男にペニスで貫かれればグウの音も出ない、ちっぽけで弱々しい存在だ。王子が認める女の存在意義はただ一つ。欲望の捌け口だ。女の順列は如何に男を悦ばせられるかに係っている。高貴な生まれも下賤な出自もそこでは一切が無価値だ。目の前のこのオーロラとて俺が姦った女の一人として間も無くカウントされるのだ。
嗜虐心に背中を押された王子は殊更にオーロラのヴァギナに鼻先を寄せクンクンと匂いを嗅いだ。
残尿臭とは明らかに異なる濃密な芳香が鼻孔を満たした。発酵した果実のような甘酸っぱいフローラルな香気に王子は咽返りそうになる。
前頁/次頁